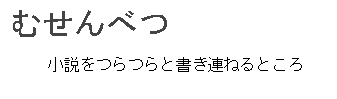3日目3
前のページに戻る/次のページに進む/もくじに戻る/
ミライは洗面所で制服に着替える。写真には何も変化はなかった。時三は半透明のま
まだった。これがどういうことを示しているのかは具体的なことは分からない。だが、
未来は何か不吉なことが起こる気がしてならなかった。
椅子に腰かけ、電話の前で時三の連絡を待つ。今は二時半。もうすぐ授業が終わり、
放課後になる。
(この二日間でとりあえず、気になるところは回った。これで何かが変わっているはず)
確信を持つことはできない。何もかも初めてのこと。事は良い方向に向かっているの
か、悪い方向に向かっているのか。それを判断できるものはなにもない。唯一の写真
も判断しかねる。
ただただ、暗闇に包まれた道を両手を出し進むように模索していくしかなかった。
何かが起きるとしたら学校以外はないのか? 時三から聞いた今までの話などを顧み
る。特に思いつく場所はない。ミライは時三の連絡を待つだけだった。
ミライは顔や腕をさすりながら時計を見る。まだ授業が終わるには時間がある。
ポケットにしまってある懐中時計の蓋を開けデジタル表記の年号月日時間を眺め、エ
ネルギー残量を見る。
(タイムスリップはあと一回だけ。これで、おじいちゃんのいる未来に戻れなかったら
あたしはどうなるんだろう...)
二の腕に巻いたベルトをさすりながらボーっと考える。
(愛と仲が悪くならないで過ごす未来だと変わる。...おじいちゃんからジーサンに...。
三十年後のジーサンってどうなってんだろうな...おじいちゃんとあんまり変わってなさ
そうだなぁ。愛はどんな風になっているんだろう)
そんなことを妄想していたらあっという間に三時を過ぎていた。
「...ジーサンまだかな...」
下駄箱で何かあったのだろうか...。
ミライは学校に向かおうか迷う。入れ違いに連絡があったら、そのことが不安だった。
(でも、電話してくる時は校舎裏からのはず。学校には携帯は持ち込み禁止だった気が
する。校舎内では携帯は使わない。やはり使うとしたら人気のない校舎裏......多分)
考えだしたら電話なんて待っていられなかった。
(それに、放課後なら学校の外にも出れるし。...学校に向かおう)
ミライはもう一度腕をさすり家を飛び出す。
愛は、授業が終わり教室を飛び出す時三の後姿を眺め、帰りの準備をする。
(ふぅ...。お、おわったぁ、ってまだ、時三君を呼び出してもいないのに...。下駄箱に
はちゃんと入れた。あとは自分の言葉で伝えなきゃ...!)
今日ほど身の入ってない日はない、そう思うほど愛は張り詰めていた。
時三と何を話したのかなんてほとんど覚えていない。朝に少し話した程度しか思い出
せない。
愛は教室を出て、ゆっくり歩いた。
帰宅する生徒たちを避け廊下の端をゆっくり歩く。
多分、屋上で顔を合わせれば、この落ち着きも全て吹っ飛ぶのだろう、そんなことを
考える。
だからこの時を、この瞬間をゆっくりかみ締めておきたかった。
階段もゆっくり上る。
周りから見れば少し邪魔になるかもしれない。そんなことを考えるが三年は三階であ
り、屋上までに教室のある階はない。
四階は各教科の準備室。教員に出会うと時間を取られるかもしれない。四階は足早に
通り過ぎる。四階の階段を上れば屋上。立ち入り禁止にはなっているがドアは開いてい
る。
屋上への階段は物置き場になっている。がたついた机が屋上への道をふさいでいる。
愛は机を跨いで階段を駆け上がる。
ドアを静かに開けると外の空気が入り込む。帰り道の賑わいや部活動に励む声が遠く
に聞こえる。
屋上を覗くが誰もいない。
愛は息を呑む。屋上にそっと出る。それはまるで雪の積もった広場に最初に踏み込み
足跡をつける。高揚感とほんの少しの罪悪感。真っ白な雪の上を歩くようにゆっくり金
網のそばまで行く。
下には校門が見える。帰宅する学生たちで溢れている。校門近くに建っている時計が
三時半を示す。
愛は金網の近くから屋上を見渡す。何も無い屋上に椅子が置いてある。学校の机とセ
ットになっている椅子だ。
愛は椅子に近づく。
椅子は汚れていなかった。
スカートが汚れないか気にしながら愛は椅子に座る。
長い髪が風に揺れる。
誰かがここを使っていたのかもしれない。なんのためにここを使っていたのだろうか。
愛は空を眺める。青空に白い雲が流れている。
流れる雲から何かを思うわけでもない。
青空を見ても他人と違う思いは出ない。
ただ訪れる時まで何も考えず。期待と不安が渦巻く心を落ち着けていたかった。
廊下を駆け、階段を駆け下りる。教員に注意されていたかもしれないが今、時三は相
手にしていられない。
(最悪なのはすでに帰っているって言う事態。それが一番最悪!)
玄関に着く。自分の下駄箱に靴が残っているか確認する。
(......ある! まだ学校にいるんだ!)
時三は校舎から出てくる学生たちを一人一人確認する。
人の出入りが多い玄関で突っ立っていると目立ってしまうが別に気にしてなんかいら
れなかった。
(まだかな...)
同じ人の流れを見ているとボーっとしてくる。そんなことを考えていた、その時。
大男が時三の下駄箱を開けた。
「あの...そこ、僕の下駄箱なんだけど...」
男と目が合う。一瞬間が空き時三が先に口を開く。
「...そこの下駄箱、僕の場所なんだけど...」もう一度言うと。
「え! うそ!」
「いや...本当なんだけど...」
「じゃ、じゃあ俺の下駄箱はどこなんだ...」
「いや、知らないけど...」
「そんな、じゃあ俺に居場所はないのかよ...」
「いや、そんなことないでしょ、多分」
「あるのか! 俺の居場所!」
「いや、知らないけど」
「じゃあ、ないのか俺の居場所...」
「...もしかして森本さ...先輩?」
「あぁそうだ、留年した森本だよ。あ、先輩なんて呼ばなくていいから森本で良いよ」
「あ、わかりました」
「敬語なんかじゃなくてもいいぜ。気軽に接してくれよ!」
「わかり...わかったよ、森本」
「おう、それで頼む!」
「で、森本はなんで僕の下駄箱を使っているの?」
「俺去年までこの場所だったんだよ」
「あぁ、それで。...じゃあ先生に聞いてくればいいんじゃない?」
「その手があった! お前良い奴だなぁ! おい! あ、そうなると俺、上履き間違え
てないか?」
「そうだね」
「いやーすまねぇすまねぇ」
そう言って森本は上履きを時三に返す。
(上履きを返してもらったけどこれだけなのか...?)
「じゃあ俺は下駄箱の場所を先生に聞かねぇとな...。えーっとお前名前なんて言うん
だ?」
「時尾時三だよ。みんなからはジーサンってよばれてるんだ」
「そうか...ジーサン! サンキューな!」
森本は立ち去ろうとする。
(何もないのか...? このままじゃあ...)一瞬脳裏に愛の顔がよぎる。
「待って!」時三は思わず大きな声を出す。
「ん? なんだ?」
「待って...」
(愛がよそよそしかったのは今日からだったのか? よく考えるんだ...。未来が接触し
てからの日常を...)
「おいおい、どうしたんだよ。いきなり考え事か?」
「あ、あのさ!」
「ん、なんだ?」
「その、今日下駄箱に何か入ってなかった」
「ん? あぁ! 入ってた! 紙切れが入ってたわ!」
「そ、その紙は! どこにあるの!」
「落ち着けって...ちゃんと持ってるよ......ほれ」森本は鞄から手紙を取り出す。
時三はしばらく手紙を持って動けなかった。
(もし、これを見つけることができなかったら...僕は...)
「俺はまだ中見てないぜ。二か月も休んでいたから期限切れかと思ってたからな」
「もう、休まないでちゃんと学校来ないとね」
時三は手紙の封を開け中身を見る。
―――放課後、屋上で待ってます。
ただその一文だけがあった。
時三にはそれだけで誰の手紙かわかってしまった。
(愛の字だ...。......もしかしてこれって...)
時三は目頭が熱くなるのを感じた。
(...昨日愛は朝早く学校に来て僕の下駄箱に手紙を入れようとしていたのか。だから、
なんとなく違和感があったのか。こんな手紙をとなりの席の奴にだしてればよそよそし
くなるよ...)
「......ばかだな...」
「ん? なんかいったか?」
「いや、、なんでもないよ」
「おおーっと俺は無粋なことは聞かないぜ。それじゃあ俺は帰るかな」
「おい、ちょっとまてよ」
突然時三と森本の背後から見知らぬ声がした。
森本と時三は見知らぬ声のする方に振り向く。
「あいつ...同じクラスの川戸山だ...」
「知っているのか? あまり良い噂は聞かないよ...。結構危ない奴らしいし...」
見た目不良の学生が四人。
「そこのでけぇのが森本だったよなぁ」川戸山が森本に近づく。
「あぁ...そうだけど」
「悪いけどちょっと裏まで付き合ってもらうぜ」
「裏って...どこだよ」
「あん? うるせえよ、ついてくればいいんだよ」
「ジーサン...お前は早くその手紙の子のところに行くんだ」森本が時三に小さく呟く。
「おい、そっちの奴も来い、一人も逃げさせないぜぇ...」
ゆっくりと他の三人が時三と森本の後ろに回りこむ。
「くそ...わりぃ...ジーサン、なんか巻き込んじまって」
「僕は大丈夫...だと思う、多分」
時三は青ざめていた。まさか自分が不良に絡まれるとは微塵にも思っていなかった。
不良なんてどこか知らない世界の生き物、まず自分の世界には関わることのない者だと
思っていた。
「森本は喧嘩っていつもしてるの?」
「いや、俺は喧嘩なんてしたことねぇ...」
「え? でも喧嘩で...その、留年したんじゃないの?」
「...俺は喧嘩なんかしたくないんだ。前の時もそうだ。向こうからふっかけてきて抑え
込もうとしたところに俺は咄嗟に手を出しただけだった。俺は絡まれたのはこれで二回
目だ」
「二回目ってことは、留年した時以外は絡まれたりしたこと無いの?」
「あぁ。なんか学校ではすごい噂になっているらしいが、完全に一人歩きだぜ...」
時三と森本は校舎裏まで連れて行かれる。周りを見ても不良四人に囲まれ、逃げ道は
無い。
「お前がなんで呼ばれたか分かっているよなぁ?」
川戸山は森本に凄む。
「いや...全く身に覚えが無...」
不良はしゃべっている途中の森本に向かって振りかぶって拳を突き出す。
それを咄嗟に両手を広げて森本は防ぐ。
「なにすんだよ!」
「おい、そいつを殴ってやれぇ」
川戸山からの命令を聞いて他の一人が時三の腹に勢い良く拳をねじ込む。
「ぐぅ...!」
時三は一瞬何が起きたのか分からなかった。川戸山が命令を出し、次の瞬間腹に激痛
が走った。
森本が叫ぶ。時三にその声は届かない。起きているのか寝てしまっているのか、その
間を行き来しているような、意識が飛び飛びになっていた。
時三は咳き込み、徐々に痛みと意識がはっきりしてくる。
でも、思考ができない。ただ目の前の地面だけが見えている。考えることが出来ない。
時三は地面に肘と手をついていた。あぁ殴られたんだ、と確認するのに何秒もかかっ
た。
時三はこれが殴られる感覚かと思うことだけでいっぱいだった。
「ジーサン! 大丈夫か!」
「うん...大丈夫、多分」
「結構タフじゃねぇか!」
川戸山は軽く笑う。
「おい! ジーサンは関係ないだろ!」
「あぁん? 関係ないからやるんだろぉ...。お前の友人が理不尽に痛めつけられたらど
う思う? しかも痛めつけられる理由がお前がムカつくからっていう理由ならよう...」
川戸山はいやらしい笑みを浮かべる。
狂ってる...。時三はその言葉だけが浮かんだ。
「お前が俺の攻撃を防ぐんだったらそこのお友達には気の毒だけど殴られてもらうぜ
ぇ」
「ちっくしょう...」
森本は動けないでいた。どうすればいいのかわからない。森本が動けば時三が殴られ
る。かといって、このまま殴られれば、この不良のことだ。森本だけですまないだろう。
「あぁん? おいなんだその手紙は? そいつを見せろ」
時三は抵抗する間も無く手紙を奪われる。
「...くく、屋上で待ってる子がいるんじゃねぇかぁ。こいつは悪いことしたなぁ。俺ら
が連れてってやるよぉ」
川戸山は新しいおもちゃを買ってもらえた子供のように目を輝かせる。
(最悪だ...。まさか、こんなことになるなんて...)
時三はふらつきながら立ち上がる。
「くく...お前はもういいやぁ」抑揚のない声は飽きてしまったおもちゃを手放すように
聞こえた。
川戸山は振り返り森本の腹に拳をめり込ます。
「ごほっ...!」森本は体をくの字に曲げる。
さらに森本の頭を掴んで膝蹴りを顔面に入れる。
森本はうつ伏せに倒れ動かなくなる。
うつ伏せの森本に蹴りを加え時三のほうを見る。その眼は蛙を見る蛇のもの。
「さっさと歩け」
不良たちに押されながら時三は屋上に向かった。
前のページに戻る/次のページに進む/もくじに戻る/