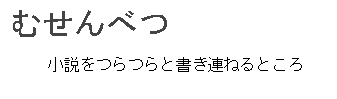12日目1
前のページに戻る/次のページに進む/もくじに戻る/
十二日目、金曜日。朝はいつも通り目が覚め、家を出る。人通りの少ない通りを出て通
学路となっている通りに出ると学生が蟻のように一点を目指してまばらな列を形成してい
る。マナもその列に加わる。今日はなんだかいつもより騒然としている気がした。なんと
いうか広いホールを大勢の人がそれぞれ話したいことを話している。全ての会話がノイズ
であり、拾うことの出来ない音。そんな感じだ。
「あ、マナだ」
マホの声が聞こえた。振り向き「おはよ」と挨拶をする。
「あ、おはよ」
マホが両手を前に突き出していた。多分マナを持ち上げようとしたのだろう。
「よく気付いたねー。はっ! もしかしてあたしマナと以心伝心になるほどの仲に?!」
そうだったとしたら、マナの気持ちは伝わっていない。いや、分かっててもマホはマナ
のことを持ち上げそう。
「お、ちっこ…のとレ…みっけ」
今度はケンの声が聞こえた。先ほどのようにマナは振り向き「おはよ」と挨拶する。
「おう、おはよ……どうした?」
「今、ちっこいって言った?」
「いんやー言ってねぇけど、でも勘良いな。ちっこいのと変な奴がいるとは思ったぜ」
「ちょーっと、変な奴ってあたしのこと?」
「お! お前も勘良いなぁ! せいかイ…ワバッ!」
ケンの奇声と同時にマホの突きが入る。確かに今日はなんか勘が良い。なんていうかガ
ラスケースにミルクを垂らすように染み込むことなく広がり、張り巡らされている感じが
する。
「あ…みん…だ」
示し合わせたかのように今度はシカバネの声が三度振り返り挨拶を交わす。
「あ、おはよ…どうしたの?」
顔を見続けていたからか、シカバネに質問を投げられる。
「今日はとても勘が良いの」
ちょっと得意になって言ってみたりする。みんなは不思議そうにマナを見る。マナだっ
て不思議だと思う。けどこういうことが起きると何か良いことがありそうな気がしてしま
う。
学校に着き席に着く。チャイム五分前を切り、廊下は騒然とする。でも、何を言ってい
るかは分からない。耳を傾けると今日抜き打ちテストがあるとか、放課後どこに行くとか、
何かを言っている。それに誰かの噂やら誰々がウザイやらあまり耳に入れたくないことま
で聞こえてくる。
そしてチャイムが鳴る。教室は静かになり、リンドウ先生がホームルームを始める。特
に言うこともなくすぐに先生は教室を後にする。一時間目は数学。数学は得意な方ではな
い。鞄から重たい教科書とノートを取り出す。教室は騒然としたまま授業が始まった。マ
ナは数学を扱うのは苦手だ。何が苦手って言うと、この公式の繋ぎ方が苦手。今やってい
る二次関数のグラフの平行移動だってYとXからそれぞれの移動分引いたり足したりする。
そこまではいい。次に移動したグラフと移動前のグラフの交点を求めよ。こういう問題に
なると途端に分からなくなる。一歩目はいい、でも二歩三歩と進むと何でもマナは分から
なくなる。努力が足りないと言われればそれまでだけど、こと数学に関しては分からない
問題は分からない。もし数学に対するやる気も才能だと言うのならマナは才能はないほう
だろう。全くやらないわけではないがテストでは一定以上の点数はとれる気がしない。レ
ベルの低い話だけど赤点を回避できれば数学はいいかなって思う。
「それじゃ、今日は六月十二日だからー…亜久、百二十六番の問題のグラフを描け」
数学の先生はたまにわけのわからないことをする。日付と出席番号が同じ人を指す振り
をして全く関係のない生徒を指す。幸いマナはグラフだけは描いていたので言われたこと
はこなせそうだったが、黒板の前にでて数学の先生からチョークを受け取る。しかし、黒
板の位置が高くなっておりグラフが描けない。黒板の下にはレバーがついておりそれを握
りながら黒板を下げることは出来る。だがマナは小さいことと力がないため、硬くておっ
きいレバーを握ることができない。
「あぁ、すまんな」
先生は思い出したようにレバー握りながら黒板を下げる。
「…く。亜久は相変わ……ちい……な、脳……も小学…並なんじゃ……だろうか。こ…馬
鹿が。さ…がZ組…な」
空き缶を後ろに放り投げるように黒い音をぶつけられた気がした。黒い音に心臓がギュ
ッと握られる感覚。上あごが締め付けられなぜか涙腺が緩む。今この先生は何をしたの?
教室は先ほどのように騒がしい。グラフを描き終え蝋でできた仮面のように表情を固くし
て自分の席に戻る。
「はい、じゃあ次を足立」
次の生徒を指名してマナが描いたグラフを消す。マナのグラフは間違いだったらしい。
それより、今の音は何だったのだろうか。席に戻りシャーペンを手の中で転がしながら考
えるが、あまりにも唐突すぎて考えようとする自分と動揺する自分がコーヒーとミルクの
ように混ざり合う。
一時間目はいつの間にか終わった。そして二限目の授業は一時限目の音が気になって集
中できなかった。マナが聞いた音はなんだったんだろうか。考えれば考えるほど、本当に
聞こえたの? と思ってしまう。そんな気がしただけ。朝から聞こえる教室のうるささが
空耳で聞こえてしまっただけではないだろうか。
なんで、こんなうるさいのだろう。朝からだ。朝から色々聞こえる。色々な色の音が聞
こえる。マホに始まり。ケン、シカバネ。みんなの声に気付いた時は何か良いことがある
と思ってみたが、なんだか、そうでもないらしい。でも、イヤなことは今日中であって欲
しい。明日はマホの誕生日だからだ。
あ、そうだ。ケンに聞かないと。マホがどんなゲームが好きか。
マナはケンが寝そべる席に行く。ケンは授業中寝ている。バイトの疲れらしいが学生と
してはどうなのだろうか。
「ケン、起きて」
ケンの肩を揺する。するとのそのそとケンは頭を上げ、眩しそうに細めた目でマナを見
る。
「…んだ。マナ…。まだ…昼休…じゃな…ぜ」
「ケン、今は二時間目。ちょっと聞きたいことがあるの」
「ぁんだ? 聞きたい事おー…って」
大きな欠伸をするケンは深夜に電話で起こされたように眠そうだった。
「マホってどんなゲームが好きなの?」
「マホが好きなゲーム? ゲーム…ゲーム…」
ケンは考え出したのか、寝直そうとしているのか再び、机に伏せる。
「ねぇケン…」
「マ…ロだ…。マグ…を用意する…だ」
また音が聞こえた。ケンの声。でも違和感があった。ケンの口から聞こえたと言うより、
耳に当てたイヤホンから聞こえた感覚に近い。
「マ…ロ、マグ…。マグロ…?」
また回遊魚。でも、あのゲームをマホは持っている。あの…なんだっけ、魚が竹やり持
っているやつ…。名前が出ない…。昼休みになったらシカバネにまた相談だ。
四限目が終わる。どうしてだろう、教室がいつも以上にうるさい。いや、学校に来る時
もそうだった。何から何までうるさかった。そのことを意識しだすと余計にうるさく感じ
てしまう。
どこか静かな場所がないか。…あった、屋上に行こう。
階段を上り終え冷たい鉄のドアを開ける。立ち入り禁止であるためか、フェンス一枚だ
けで囲われた場所だ。そこの真ん中にレジャーシートを敷いて寝転がっている生徒がいる。
「シカバネ?」
彼以外ここで寝転がっていることはないだろうがなぜかその事実だけははっきりさせた
くなり口に出して確認を求める。マナの声に反応して上半身を起こし欠伸をひとつして、
マナを見る。
「…どうしたの?」
「静かな場所に来たくなったの」
屋上は静かだった。何も聞こえない。いるのはシカバネだけ。そしてその横にはフィギ
ュアの本体。
「あ…」
いない、そういえばフィギュアと話していない。一人できっかけを作れないと意味がな
いと昨日は口出ししない約束だった。しかし、それは昨日だけで今日は違うはず。あのお
しゃべりで人をからかうのが大好きなフィギュアが朝から何も発していない。
フィギュア、フィギュア。
呼んでみても、反応はない。無視を決め込まれているのか、それともマナの中にいない
のか。それを確かめる術はない。
「ん、何かあったの?」
「ん…? ああ! えぇっとね…。休み時間の間にマホがどんなゲームが好きか、ケンに
聞いてきたの」
「それでなんだって?」
「マグロを用意しろって」
「マグロ? もしかしてケンに貸していたゲーム?」
「それかも。でもそれって新しくないよね…」
「いや…あれは最近新作が出ているよ…。それに、結構珍しい作品なんだ。新しくて珍し
い物っていう点ではクリアーしているかもね」
二つの条件を満たす。さすがケンだ。マホのことはケンに聞けばもっとわかるはず。
「マナ、ケンにもっと色々聞いてくるね!」
先ほどのいくつかの悩みは机の消しカスのように取り払われる。しかしそれらは消えた
わけではない。今は机の下に落ちたが消えたり何か他のモノに変わったわけではない。け
ど今は自分に何かできることがるという躍動感でいっぱいだった。
「あ、ありがとね。教えてくれて」
シカバネにお礼を言うのを忘れるとことだった。シカバネは少し笑ってくれた。それを
見てシカバネに背を向け屋上を後にした。
前のページに戻る/次のページに進む/もくじに戻る/