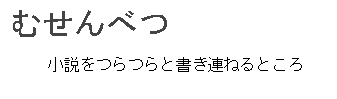その匂いに誘われて
――お腹すいたなぁ。 夕刻の帰り道にそう思ったとき。 僕は鼻をすすると食欲をそそる匂いに気付く。 一度その匂いに気付くと僕の胃は意志に背いて唸りだす。 さっきまでは別のことを考えていたのに 一度気になりだすと止まらない。 僕はその匂いの元を探るために足を止め深呼吸をする。 鼻腔にむさぼる様に空気を取り込む。 「あっちだ……」 その匂いは人通りの少ない路地から漂ってきている。 誘蛾灯に誘われるように僕は路地に向かって歩き出す。 もう頭の中はその匂いのことで一杯だ。 路地に入り僕は小さくため息をひとつ漏らす。 飲食店の看板――しかし、僕がその看板の店に歩き出そうとした時 目の端に他の飲食店の看板が目に入る。 匂いの元は……さらに奥から来ている……ように感じる。 僕は歩き出そうとするつま先の向きを変え看板の横を通り過ぎる。 匂いはどこから来ている……? 人目も気にせず鼻を鳴らしながら飲食店の看板を目を皿にして見つめる。 「あ、あれだ……!」 匂いを漂わせているであろう店には行列ができていた。 その行列を見て僕は確信する。 早足でその行列に並ぶと匂いはよりいっそう強くなる。 「なんだい若いの。あんたもここの噂を聞きつけてやってきたのかい?」 この気安さは結構年のいっているオジサン特有のものだ。 その決め付けでどうしようということはないけどそう思った。 「僕は、おいしそうな匂いがしたのでここまで来てしまいました」 薄く苦笑いを浮かべながら答える。 「あぁわかるっ! 私も匂いに釣られて来てしまいましたからねぇ!」 オジサンの前に並んでいた――誰にでも敬語で対応してしまいそうなオニイサンが 気の合う仲間を見つけたように表情を明るくする。 「表の通りにいたのに匂いがするのにはびっくりしましたよ〜。 いや〜あんまりお腹すいてないのにいつの間にか並んでいたんですがね〜!」 はははと笑うオニイサン。と、その時。 「一名様どうぞーッ!」 店の中から声がする。 「それでは、お先に」 オニイサンが小さく会釈してのれんをくぐる。 「もう一名様どうぞーッ!」 オジサンはずかずかと歩きながら店内へと姿を消す。 「お客様は一名様ですかー?」 店員が僕の顔を覗いてくる。 「えっと、ひとりです」 そう答えると。 「席はー……先ほどの方たちと相席になってしまうんですがー……」 「いいですよ」 そう答えると満面の笑顔――多分営業?スマイル――で 「ありがとうございまーすッ一名様どうぞーッ!」 そういって通されたのは先ほどの二人が座っている四人ボックス席であった。 「お、またあったなぁ! 若いの!」 オジサンは手を上げて気さくに声をかけてくる。 「いやー。相席なんて久しぶりですよねぇ!」 オニイサンはケータイをいじる手を止めて顔を上げてはにかんでいる。 それぞれの反応に返事をして席に着く。 「あ、そういえば。ここ、ケータイクーポンとかあるんですよ! 知ってます?」 席に着くといじっている手を再び動かしそう聞いてくる。 「なんだぁ? くーぽん?」 明らかに違うイントネーションを返すオジサン。 「えぇ割引してもらえるチケットのようなものなんです」 知らないことを察したオニイサンはケータイを出すように言って 横から説明している。 「チケットなのにケータイからってどういうことだよ?」 オニイサンは少し説明しづらそうにしている。 長くなりそうだから僕もケータイをいじりその割引クーポンを画面に表示させる。 「ここの一番人気のメニューがクーポンで安くなるんですね」 「そうなんですよー! 私はそれにしようと思います」 「よくわかんねぇから俺もソレで良いや」 三人ともすぐに頼むものは決まった。 店員にクーポンを見せると慣れた様子でメニューを叫ぶと 奥の厨房から声の通る返事がする。 すると、ケータイに狙ったかのようにメールを受信する。 慣れた手付きでメールを開くと 『早く帰ってきなさい! 待ってるからね!』 僕はじんわりと嫌な汗が額ににじみ出る。 ――かつて、こういうメールがきたとき僕は失念して遅く帰ったら 隠し事がバレてこってり怒られた。 それに加え遅く帰ってきたことも怒られた。 「どうしたんだぁ? 腹でも痛くなったかぁ?」 オジサンは僕の様子を察したのか笑いながら聞いてくる。 「いや、おなかはいたくないです。ただ用事ができてしまいまして」 「なんだい、そんなんとっとと食えば問題ないだろう?」 オジサンはそういう。 「そうですね〜。ここは結構出てくるのが早いからそんな時間は掛からないと思いますよ」 オニイサンもそういう。 二人は食べるよう進める。 不安は拭いきれない。けどここまでおいしそうなご飯は久しく食べていない気がする。 だけど、そういって前も帰るのが遅くなってしまった……ような気がする。 「あ、ほら来ましたよ!」 悩んでいるうちに三人前の人気メニューが運ばれてくる。 「お待たせしました。当店一番人気のメニューでございます!」 その味に自信があるのか店員は自信満々な様子でメニューをテーブルに置いていく。 その時、鼻の中にたちこめる匂いは先ほど外で感じたものだった。 「うわ〜! おいしそうですねー!」 「これはなかなか、いい感じじゃねーの!」 二人が感嘆の声を漏らす。 僕もその匂いの元凶に視線を落とすと ついつい箸に手を伸ばしそうになる。 「「いただきます!」」 二人は箸を手に取り食べ始める。 「若いの。食べないのか? さめちまうぞ?」 「そうですよ〜。こんなおいしい料理なかなか食べられませんよ?」 二人にそういわれ再び視線を落とす。 箸を手に取ろうとして引っ込めた手が再び宙をさまよう。 「さぁさぁとっとと食べれば、大丈夫だって」 「そうですそうです。ほらどうぞ」 オニイサンがそう言って箸を僕の目の前に置く。 「……あ、あの僕帰ります! お金ここ置いておくのでこれお二人で食べてください!」 僕はよく分からないが気持ち悪いモヤを振り払うように立ち上がり店を飛び出す。 手の中のケータイを覗く。なんと店に入って二十分は経っていた。 僕はなんとなくあの店に不気味さを感じていた。 あの惹きつけるような匂いはまるで撒き餌のようなものだったのではないか。 そんなありえない考えがよぎる。 家につく頃には汗だくになっていた。 「ただいまー……」 もっていたハンカチで額を拭う。眠る猛獣を起こさないような足取りで リビングへと歩く。 すると、先ほど惹きつけられていたあの匂いが家の中に充満していた。 確信はない、漠然とした不安。拭った額から汗がにじむ。 リビングのドアに手を掛けると倒れ込むようにドアを開ける。 「きゃっ!」 短い悲鳴があがる。 「あ、ただいま。……ってどうしたのコレ?」 僕は目の前の食卓に視線が釘付けになる。 普段は質素な食事が並ぶだけのテーブルには豪華絢爛という――うちでは似合わないが―― そんな言葉が似合う食事が用意されていた。 それに先ほど食べ損ねたモノまである。 「今日は誰の誕生日だっけ?」 とぼけた声でこの晩御飯を用意した本人はいう。 「そういうことかぁ……あせって損した」 「ふふ、また怒られると思ったの?」 「……わかってやったんだ」 「驚かせあげようと思ったの。あるでしょ? 誕生日のサプライズ。 それに最近距離置かれちゃってた気がしたから、はりきってみましたッ!」 「別に距離を置いてたわけじゃないし……」 「まぁまぁ、それならそれでいいの。さ、主役もきたことですし。たべましょ」 僕は先ほど食べ損ねたこともあって真っ先に箸を伸ばす。 そしてお腹が落ち着いてきた頃、やっぱり帰ってきて良かったと 感激と共にほっと安堵のため息も出ていた。 もしあそこで食べてから帰っていたら、帰りは遅くなって険悪になり食事を楽しめず 多分いままで以上に距離を感じてしまっていた……かもしれない。