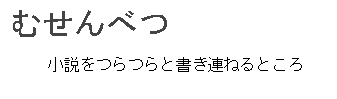しんだあの子3
前のページに戻る/
次のページに進む/
もくじに戻る/
そしてそんなステキな印象は数日の間にぬぐわれる。最初はその憧れとか、そんなも
のが頭に焼き付いていたが今ではそんなものはきれいさっぱり消えている。
思えば最初の出会いでの常軌を逸したわけのわからないやり取り。
わかっていた。わかっていたけど、あれこそがやっぱりレイの本性であった。
「マドカ、帰りますわよっ」
授業が終わるとレイは僕にそう呼びかける。陰ではレイはお嬢様で僕は召使。そう呼
ばれている。
「はいはいただいまー」
このやりとりも当たり前になり、生返事でレイのもとにいく。
――また召使のやろうがパシられてるよ。
――べつによくね。あいつもうれしそうにやってるし。
――まぁおれらにいじめられるよりはマシかもな。
などなど、いいたい放題いわれているけど、これがごもっともな話しだ。
僕はレイと話すようになってから、いじめられることはなくなった。まぁその分陰口
が増えたが実害がなさそうだから今のところは穏やかに過ごせている。
と、思っていたのもつかの間だった。
朝の朝礼が始まる前に席につく。そして一時間目の授業の教科書を取り出そうとした
時、明らかに教科書以外の感触があった。それを掴んで引き出す。それはゴミだった。
飲み終わった紙パック、食べ終わったおかしの包装紙、悪口がかいてあるであろう紙、
思いつくであろうゴミが僕の机の中につまっていた。
動揺した。最近はレイと一緒にいたおかげか、全く直接的ないじめはなかった。だけ
どそれは解決ではなかった。直接できないなら間接的にやればいいだけだった。
レイのそばにいれば大丈夫と思っていた自分にはえらく響く一撃だった。正直なこと
をいえばレイにはかなり甘えていた。レイは友達がいなくても別にいじめられない。そ
れは周りから一目置かれているからだと思う。そんなレイのそばにいれば僕もいじめら
れない。どんな陰口を叩かれても実害はない。レイのそばにいれば安全だ。
そんな考えをしていた自分を罰するかのような一撃だった。
「おはようございます」
レイが後ろから声をかけてくる。
「お、おはよう!」
僕は後ろめたさから思わずゴミを机の奥に押し込む。
「何を隠したのかしら? 天才であるこのわたくしに隠し事を通せると思っている
の?」
このストレートな性格。普段は頼もしいけどこうやって相対すると非常にやっかいだ
った。
レイは肩に手を掛けてにやにやしながら机に視線を向ける。
「さて、なにを隠したか。言えることはわたくしには見せたくないものですわね」
「うん……」
「あえてみせてみません? ソレ」
「なぜみせたくないかわかってて聞いてるんでしょ?」
「ええ、もちろんですわ。それでも気になってしまいますわ。友達の反応というものが。
そこに隠しているのはきっとわたくしに対してうしろめたい、もしくはわたくしが見た
らブチキレるものですわね。それか、マドカ自身がみせたくないものか。先ほどの反応
だけですとそれくらいしか推測できませんわ」
「レイが気にすることじゃないよ。ほら先生くるよ」
「ふふ、話したくなったらいつでもいいですのよ」
そういってレイは席につく。そんなこといわれたら余計にいえなくなってしまう。レ
イに甘えちゃだめだ。
僕はレイの目がつかないようゴミを捨てる。授業が終わって放課後になる。いつもな
らミミと話をさせてくださる? とレイに押しかけられるがその前に逃げるように屋上
へと退散する。
ひとり屋上で端に腰掛ける。別に用事のなんてない。ただ逃げるためにここに来たん
だ。時間をもてあまし手持ちぶさたになってしまいケータイを取り出しいじる。
といってもこのケータイは機能らしい機能が全くない。アラームやカレンダー表示な
んてものもない。ただ画面にはデジタル表示ででかでかと時間が刻まれているだけだ。
唯一の機能、電話をかけようかとアドレス帳を開く。
――ミミに電話してみようか。
そんなことを考えるが、電話したところでなんの意味がある。また初めて電話をかけ
たときのように情けない話をしろというのか。
そう思ったらなんだか笑えてきた。見た目も体つきも性格も貧弱という理由でいじめ
られて、さらに女の子に守ってもらって……。
多分これ以上情けなることはない、と思う。
けど、やはり情けないことに変わりないからか電話をかける気にならない。一度そう
思ってしまうとどうでもよくなり、ほこりまみれの屋上に寝転がる。
その時、ガチャっと屋上の扉の開く音。誰かが来たのだろうけど反応するのも億劫だ。
扉に背を向けて寝ていると目の前に、先ほど見かけたようなゴミがばら撒かれる。僕
は弾かれるように飛び起き扉のほうを見る。
「あなたにプレゼントだそうですわ、ソレ」
レイがふんぞり返るように立っている。その表情は険しい。
「なっさけないですわね。これはどうみてもいじめらていますわ。わたくしと一緒にい
るようになってからは目に付くいじめはなくなったと思っていたのですがこんなことや
っているなんて」
レイはどうやらゴミを入れた誰かのことをいっているようだった。僕はレイがぷんす
か怒る様子をただぼーっと見ていた。
「あなたもあなたですわっ」レイはビシッと僕に人差し指を突きつけ眉をひそめる。
「どうしてわたくしにいわないのです? わたくしに申してくれればすぐに沈静できる
というのにっ」
「ごめん……」
「いわなかった理由を説明していただけるとこの怒りも収まるのですがっ」
眉間にしわがよりっぱなしだ。このままだとレイはずっとそんな顔をしていそうだ。
「またいじめられだして思ったんだ。僕はいじめられないようにレイを利用していただ
けなんじゃないかなって、それで今回ゴミを入れられた時に、レイに言うのが後ろめた
くて……」
「利用していて後ろめたいから言えなかった。そう仰るんですわね。ならわたくしもあ
なたを利用していることになりますわ」
レイは僕の手に握られているケータイを指差す。
「わたくしはそのケータイのオーバーライセンスの構造を知りたいがためにあなたに近
づきましたわ。あなたの言い方で言えばわたくしはあなたを利用してそのケータイを調
べていますっ。どうです? これであなたの後ろめたさというものはなくなるんじゃな
くて?」
「レイはそういうけど、僕は別にレイがケータイを調べるために僕と一緒にいてくれる
のはいやじゃない。だから、その……」
「あーら、だったらわたくしも同じですわ。別にあなたが一緒にいていやだと思ったこ
とはありませんことよ?」
なんだかだまされた気分だ。僕はそうおもったけどいやな気持ちはなかった。むしろ
嬉しくて笑みが綻ぶ。
「レイはすごいよ。僕とは全然違うね」
レイはいつもどおりふんぞり返り言い放つ。
「天才ですもの。ま、でも、わたくしもマドカと同じですわ。友達というのはあなたが
初めてですし」
「レイは友達いないの?」
「えぇおりませんわ。教室であんな扱いをされていて、いるわけないと思いません?」
「じゃあ、レイも友達っていうのがどういうものか知らないんだね」
なんでも知っていそうなレイにも知らないものがある。なんだかそれがうれしくて思
わず小さく笑ってしまう。
「む、どうしてうれしそうに言うのかしら。確かにわたくしは友達がいたことをはあり
ませんわ。けど、友達というのは何か悩みがあったら相談できるものじゃなくて? わ
たくしはそうであって欲しいですわ」
レイの言う通りだ。僕も友達はレイの言う通りであって欲しい。そう思ったら話して
しまった方がいいんじゃないかと思えてきた。
「なんだかへんなことで悩んでいたみたい」
「やっとわかったようですわね。それで朝も同じようにやられたんですの?」
「うん、そうなんだ」
僕はレイが持ってきたくしゃくしゃになったゴミのひとつを掴み取る。
「なんでこんなことをやるんだろうね」
朝、机の中に入っていたゴミの一つ。悪口が書いてあるであろう紙を思い出した。
僕はくしゃくしゃになった紙を広げると。
『鳳華殿様にちかづくな』
紙にはそう書いてあった。
「それを書いたのは、カタブチですわね」
「どうしてわかるの?」
「律儀に鳳華殿様なんて使うのは彼くらいですわ。周りの方はそんなカタブチを面白が
っているだけですわ」
そう言うとレイは屋上の出入り口の方に歩き出す。
「レイ、どこに行くの?」
「今までは別に大して腹が立つこともなかったんですが、今、わたくしは妙にむかつい
ていますわ」
「待って、レイ」
僕はひとつの考えが閃いた。カタブチ君は他の生徒よりレイを恐れている。こんなこ
とをするのだろうか。
「もしかしたらカタブチ君は違うんじゃないかな?」
「違う? どういうことですの?」
「カタブチ君は僕かレイがいじめられるのを気付いていたんじゃないかな」
「……面白い考えですわね。聞かせてくださる? その話を」
「カタブチ君はクラスのみんなといつも一緒にいないでしょ?」
「あら、どうしてわかりますの?」
レイはフフっと僕を試すように笑う。
「だってカタブチ君はレイのことを様付けで呼ぶんだよ? それって、とてもヘンな奴
に見えると思うんだ」
「あなた一人の感想じゃあ根拠――理由としては弱くなくて?」
「これは僕一人だけじゃない。レイもさっき言っていたでしょ? 『周りの奴はそんな
カタブチを面白がっている』って」
「えぇ、言いましたわ。さて、マドカは一体何をおっしゃりたいですの?」
「つまり……カタブチ君も僕と同じようにいじめられているんじゃないかな。僕のいじ
めは最近はなかった。それっていじめがなくなったんじゃなくて。相手が変わっただけ、
なんじゃないかな」
話を言い終わってもレイは、じっと僕の目を見て黙っている。
「何か……違ったかな……」
「何も違ってはいませんわ。けどマドカ。それじゃ足りませんわ」
「足りない……?」
「今マドカが話したのは説明ですわ。じゃあ、それに対する答えは、一体何なんですの?」
レイは人差し指をビシッと僕につきつける。
「答え……」
レイの勢いに思わず一歩後ろに下がってしまいそうになる。
だけど、僕の中に答えはある。
「それは、カタブチ君をいじめから助ける。そのために友達になる」
「あら? 友達に? 発想が飛躍してなくて?」
「飛躍っておかしいってこと? 別におかしくないはずだよ。だって僕はレイと友達に
なってからいじめられなくなった。なら友達になることが助けることなんじゃないかな」
言い切るとレイはフッと小さく笑う。そして
「ふふ、ふふふ、あははははは!」
と大笑いをしだす。
「ど、どうしたの?」
「あははは。はぁはぁ。ごめんなさい。笑うつもりはなかったんですの。マドカの言っ
ていることは、まぁ正解ですわ。あまりにも真っ直ぐな答えだったんで、わたくしが恥
ずかしくなってしまいましたわ」
「な、僕ヘンなことを言った? これってレイが僕にやったことじゃないか」
あまりにも笑うから僕はなんだか恥ずかしくなりちょっと。不機嫌そうに言ってしま
う。
「申し訳ございませんわ。さ、行きましょ」
「ちょっと、行くってどこに?」
歩き出すレイの背中に声を掛ける。するとレイは何を今更と笑い答える。
「あら、カタブチを助けに行くんじゃなくて?」
「さすがにわたくしでも誰がどこにいるかは把握しておりませんわ。手分けして探しま
すわよ」
そう言って僕等は別々にカタブチ君を探すことにした。
だがいざ彼を探そうとしても僕には全く手がかりがなかった。
カタブチ君が放課後何をしているのか。さっさと家に帰ってしまうのか、それとも放
課後も校内にいるのか。
あらためて、考えると自分が他の人に目を向けてないなと思ってしまう。目を向ける
ときといえば誰かが何か問題を起こしたりした時だ。
いじめられていた時は考えもしなかったが問題ごとが起きた時、ただそのことを眺め
ているだけというのはなんだか悪いことなんじゃないかと思えて仕方なかった。
けど、だからってどうしようもないこともある。
レイは助けてくれたけどレイは普通の人に比べたらちょっと違う。レイだから助けら
れたんだ。普通の生徒だったら、きっと助けられるものじゃない。
僕はカタブチ君を助けられるのだろうか。
いつも僕を追い回していじめていた奴らからカタブチ君を助けられるのだろうか。
「おい! そっち行ったぞ!」
いじめていた奴の声。僕は声にすくみ上がりながら声のした方を見る。
すると、廊下の角からカタブチ君があらわれた。僕と目が合うと、顔を恨めしそうに
歪ませ僕とは逆方向に走り出す。
が、しかしカタブチ君が逃げた先にもいじめていた奴の仲間が回りこんでいた。
「おい、カタブチ。おめぇ、鳳華殿サマーにはわからないようにやれって言ったよな?」
肩を思いっきりど突かれ尻餅をつくカタブチ君。
助けなくちゃ……!
そう心の中で叫ぶ。
だけど、体はすくんで動かない。
僕が助けにいってもいじめる彼らを止めることはできない。
そんな考えがよぎると足は一歩も前に動かなくなる。
だけど一歩後ろに下がると吸われるようにもう片方の足が下がる。
そして、僕は
「せっ、せんせー! ここでいじめてるやつがいます!」
そう叫ぶといじめている奴らは驚き、僕の方を見る。
「カタブチ君! 逃げて!」
カタブチ君は立ち上がると
「おい、逃がさねーぞ!」
いじめている奴らはカタブチ君の道を塞ぐ。
「あ、せんせー! こっちです!」
と再び叫ぶと、奴らはこっちに気をとられる。そのスキをカタブチ君は見逃さず走り
出す。
「おい! マト。てめぇ、最近鳳華殿と一緒だからってちょーし乗ってんじゃねーぞ!」
奴らのターゲットが僕へと変わった。これでとりあえずはカタブチ君が追われること
はなくなった。
でも今度は、僕が走る番だ。
けど、あそこでカタブチ君を助けなかったら、きっと友達にはなれない。
「先生、呼んだってのもどうせ嘘なんだろ!」
僕はすぐに追いつかれると、服を引っ張られ床に叩きつけられる。
「てめぇ、まだやられ足りないようだな……」
いじめっ子のリーダーは低く唸るような声で僕の方に歩いてくる。
「あら、やられたりないのは、あなたではなくて?」
レイの声がした。
「あん? ブッ!?」
と思った次の瞬間いじめっ子のリーダーが床に伏せている。そして頬を押さえながら
見上げる。
「鳳華殿ッ……!」
「あら、『様』はつけてくださらないのかしら?」
「クソがァアアア!」
「分を、わきまえなさいっ!」
レイは飛び掛ってくるリーダーに思いっきりビンタを喰らわす。
パチンと乾いた音じゃなかった。ゴッて音だった。なぜならリーダーは廊下の壁に顔
をめり込ませられていたからだ。ついでに間抜けな顔もさらしていた。
「や、やめはがれッ!」
「あーら、なんておっしゃっているかわかりませんわ」
壁に押し付けるレイはそれはもう意地悪そうな笑みを浮かべている。
「マドカ、いまのうちにカタブチを追いなさい」
「う、うん」
僕はカタブチ君の走っていった方に走り出す。
「まひやがれッ!」
「待つのはあなたたちですわ。一人でもマドカを追いかけようとした瞬間に壁にめり込
ませますわよ」
レイはもう片方の手をにぎにぎさせる。それを見て誰も動き出そうとする奴はいなか
った。
「カタブチ君!」
カタブチ君は教室から窓の外を眺めている。僕が声をかけるとゆっくりと僕の方をみ
る。
「君は鳳華殿様にいっつも助けてもらってるな。情けなくないのかい?」
不意な質問に思わず面食らう。けどカタブチ君は真面目な表情で僕を見ている。
「情けないとは思ってないよ」
「ふーん、そうか」
カタブチ君は再び窓の外を眺める。
「カタブチ君はどうして情けないと思うの?」
僕が聞き返してもカタブチ君は窓の外を眺めて話そうとはしない。
何も話さないならこっちから話していくしかない。
「レイは友達だ。友達と助け合うのは別に情けないことじゃないと思うんだ。それに…
…
「俺の家は鳳華殿様のおかげであるようなものなんだ。友達とかそういうレベルの話じ
ゃない」
「それは、大人の話でしょ。レイは関係ないんじゃないの?」
「関係ないわけないだろう? 鳳華殿家の娘なんだぞ。なにか問題でもあってみろ。俺
の家はまた一家離散だ」
必死に抑えているが声には震えが混じっていた。カタブチ君の家で何があったのかは
わからない。きっと僕には想像できないような辛いことがあったのかもしれない。
「なら、カタブチ君はひとつすでに問題を起こしているよ」
そう言うとカタブチ君は表情を強張らせ僕を見る。
「なんだと……?」
「レイはね、自分を鳳華殿って呼ばれるのを嫌っているんだ。それに様付けで呼ばれて
ちゃ周りから距離を置かれて友達が出来ないって文句言ってたよ」
「そんな……」
カタブチ君は頭を抑えて表情がみるみる歪んでいく。
「ねぇ、カタブチ君。どうしてそんな怖がっているの?」
「だって……鳳華殿の娘……なんだ……」
「君は、レイと話したことある?」
「そんなこと、恐れ多くてできるわけないだろう……!」
「じゃあ、レイの嫌いなものは? 好きなものは?」
「知らない……!」
「なら今度さ、レイと話してみなよ」
「鳳華殿様と……?」
「それにその『鳳華殿様』もやめた方がいいよ。さっきの奴らが面白がるだけだしさ」
「ほうか……レイ、様は……その、お怒りになられているのか? 今までの呼ばれ方で」
「ううん、君が思っているほど、レイは怖い子じゃないよ。……いや、まぁたまにいろ
んな意味で怖くなるかな。でも、本気で怒っているわけじゃない。むしろ、心配してい
たかも」
「誰の心配をしているんだ……?」
「カタブチ君のことだよ。僕の机の中のゴミだってさ、カタブチ君が最初にメモを書い
た紙を入れたんでしょ」
「…………」
「あれは悪口じゃない、レイはそれに気付いたんだ。それで君もいじめられているんじ
ゃないかって心配して助けにきたんだよ」
「なんで……。さんざん迷惑をかけたというのに……。どうしてそんなにしてくれんだ
……」
「それはさ、友達になりたいからじゃないかな?」
カタブチ君はまた窓の外を眺めながら黙ってしまった。
僕もこれ以上何を言えばいいか、わからず黙っていた。
長い沈黙の後、カタブチ君は僕を見る。
「すまなかったな、マト。俺は一人で無駄なことをしていたんだな……」
「そんなことないよ。僕の机に入ってたメモは僕のことも心配している内容だったんじ
ゃないかな。僕はそう読んだんだけど」
「マトはお人好しだな。だから目をつけられるんだよ」
「あぁ、なるほど……。なんとか直したいとは思っているんだけどね」
「いや、でも、だから俺は色んなことに気付けたんだ。ありがとな、マト」
カタブチ君はそう言って帰っていった。これで、とりあえずは良かったのだろうか。
レイとの妙な壁もなくなったと思う。
「フフ、うまくいったみたいですわね」
教室にレイが入ってくる。
「レイ、あれさっきの奴らは?」
「全員帰らせましたわ」
手をニギニギさせながら答える。どう帰らせたかは聞かないでおこう。
「いま、そこでカタブチに会いましたけど、「さようならレイ様」って言われましたわ」
「あれ、様付けだったんだ」
「ふふ、些細なことですわ。一度一歩進み出せばあとは歩くだけですもの」
「それにしても、レイはどうしてカタブチ君に呼び方を直すよう言わなかったの?」
「あら、言ったじゃないですの」
「そうじゃなくてさ、もっとこうちゃんと言ってなかったじゃん」
「そうですわね、マドカには言っておいてもいいかもしれませんわね。カタブチ家は鳳
華殿家が助けるまではお金に困って生活が非常に苦しかったらしいんですの」
「いっかりさん? って言っていたね」
「……その時に母親が、いなくなったそうなんですわ」
「いなくなったの? どこに?」
「知りませんわ。それに昔の話ですわ」
レイは背を向けてさっさと歩き出してしまう。僕もすぐに鞄を持ってレイを追いかけ
た。
前のページに戻る/
次のページに進む/
もくじに戻る/