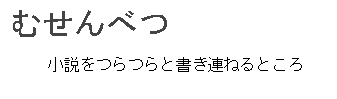とある街で2
前のページに戻る/
次のページに進む/
もくじに戻る/
「最終シーケンスを終了します。以上メンテナンスを終了。これより通常運転へ移行し
ます」
ミミの淡々とした声が聞こえてくる。俺は頭をすっぽり覆うバイザーを外す。
「……サイバーダイブを終了します」
俺は現実に戻ってきた。するとすぐにどこからが現実でどこから『中』だったかを思
い出す。朝起きてシャワーを浴びてこの部屋に来てメンテナンスを開始した。そこまで
が現実で、ファイルに数値を記録したという部分はミミの『中』での出来事だ。
「毎回サイバーダイブは現実なのかミミの『中』なのかわからなくなるよ」
サイバーダイブシステムはノリコさんが発明したシステムの一つだ。これはあらゆる
ものを機械の信号へと相互変換するシステムだそうだ。
さっき俺が現実だと思っていた世界はミミの『中』の思考回路やミミに見えている世
界だ。本来は機械の信号で成り立っているミミの世界を見ることは出来ない。けどサイ
バーダイブシステムを使い人の視界として認識し、ミミの世界を見る。もしミミに何か
異常があれば世界に歪みが出来るらしい。だが今日まで一度も異常が出たことはないか
ら歪みというものがどういうものなのかわからない。毎日ミミの『中』から記録をつけ
ているが、何か見逃してなければいいんだけど。
俺はため息をつきながらパソコン越し椅子に座っているミミを見る。
するとミミは椅子を立ち俺の元に歩み寄り、そして、いきなり胸元に、俺をうずくま
せるようにギュッと抱きしめてきた。
「ちょ、ちょ待て。何やってんの?!」
「とっても怖がっているように感じたから安心させるために抱きしめてみました。どう
です? 落ち着きます?」
「お、落ち着かないよ! 逆に落ち着かないよ!」
ミミの胸はとても柔らかく、ない。むしろ機械特有の丈夫さというか硬さというか人
のソレに触れたことのない俺はコレを硬いとしか表現できない。俺は慌ててミミを引き
離す。
「こんなことどこで覚えたんだよ?!」
「アレですね。心臓の音は人を落ち着ける効果があるとネットで知りましたので、検証
するにはこれはチャンスとおもいましてですね」
「……突っ込みたいところしかない説明だな。まずいつの間にネットなんかで調べたん
だよ」
「ミミはずっと家でお留守番ですからとても暇なのですね。最近新しく始まったテレビ
の番組はつまらないですし」
目の前のロボットはなんだかロボットにあるまじき発言な気がする。これがロボット
の心だというのなら専業主婦の心とロボットの心は大差ないのではないのだろうか。
「それと心臓の音を聞かせるということに関してはまず検証できないことに気付きまし
た。なぜなら、ミミには鼓動というものがないのですネ。がっかりです……。そうだ、
今度所長につけてもらうってのはどうですか?」
ミミは胸に手をあて名案だといわんばかりの笑顔を向けてくる。
「いや無理でしょ。心音を鳴らすためだけにミミを改造するお金も理由もないし」
「お金はありませんかもしれませんけど、理由はあります! ズバリ、マドカを落ち着
かせるためです!」
「だから、落ち着かないって。逆に」
「なら、どうすれば落ち着くのでしょうか?」
「いやいや、俺はいつも落ち着いているでしょ?」
「そうでしょうか? ミミ知ってますネ。マドカが早く起きてきた日はレイの夢を見た
ときだって」
「……そういえば、そんなこと言ったことあったようなないような。けど今はもう大丈
夫だよ。さすがにいつまでもウジウジしてらんないしさ……って変な空気になっちまう
からこの話しはおしまいだ。ミミ、お前からみて体とかに異常は特にないよな?」
「はい、大丈夫ですネ。今日も元気です!」
「じゃあ俺は飯作ってくる。早く起きちゃったからミミのも用意しよっか?」
「え?! いいんですか? ならミミも食べます!」
「何食べる?」
「はい! マドカと同じのでお願いしますね!」
「それじゃ準備できたらリビングに来いよ」と言って研究室を出る。リクエストを聞い
てはみたが俺が用意できる朝食はトーストを焼くこととサラダを盛り付けることだけだ。
オーブンにトーストを二枚入れる。いい感じの焼き具合になったら取り出すからテキ
トーにおもいっきりダイヤルを回す。その間にサラダを用意する。サラダは昨日のコン
ビニの残りだ。
そして次にテーブルを見て、ため息をつく。
「やはりノリコさんは資料をばら撒く天才だな」
テーブルの上にもノリコさんの資料が散乱している。
普段はミミが昼間の間に家の中を掃除をしている。一応研究室の中はかなーり重要な
資料もあるから掃除はしなくていいとなっているが、研究室の外まで資料が侵食してい
る。
もし、ミミがこれを見て、いらないと判断したら捨ててしまう可能性がある。
ノリコさんが取り扱っている資料の一枚をそっと掴み取る。
「『ファントム社によるクローン体の今後の扱いについて』、『サイバーダイブシステムの
技術提供の未払い期間について』ってこれはなんとなくわかる。うちのサイバーダイブ
システムをどっかに貸しているってやつなのか?」
たかだか高校一年生の俺には知りようのない雲の上の話に感じる一枚であった。
「下手にいじらない方が絶対いいな……」
テーブルの上に散らかった紙を脇に抱え研究室に向かう。
「おーいミミ、開けるぞー」
「へい、お待ちですね!」
声をかけると威勢の良い声と共にミミがドアを開ける。
俺はミミの頭からつま先まで見てもう一度頭を見る。髪型はツインテールに結ってお
かしな感じはない。だが、俺はいつも気になってしまう部分がある。
それは髪留めだ。ミミの髪留めはよく見るとワニぐちクリップという洗濯ばさみのよ
うなもので結ってあるのだ。
ワニぐちクリップというのは豆電球と電池の間につける電圧計。それのプラス極やマ
イナス極に挟むやつだ。ご丁寧にミミのクリップは左右で青と赤になっている。
一応装飾品らしくかわいく施されているが、一度気付くと気になって仕方がない。洗
濯ばさみを髪留めにする女の子が世界中を探して他にいるのだろうか。もしかしたらミ
ミと同じような感じでいるのかもしれない。
「えへへー、どうです? ちゃんとできてますでしょ?」
ミミが頭を振って見せつけてくるから俺はおもむろに青い方をつまんで外す。すると
髪は音もなく崩れる。
「ああぁ! か、返してくださいネ! もぉー!」
ミミは取られた方の頭を抑えながら泣きそうな顔でクリップを要求してくる。なんだ
かとても悪いことをしたように感じてしまうじゃないか。
「あーごめん、クリップがあまりにも気になってしまったもんで」
「やめてくださいねー! ミミこれがないと外に出れないんですからね」
「わりぃ、洗面所で直してきてくれ。そしたら飯にしよう」
ミミのクリップはただの飾りじゃない。あれはバッテリーとなっており、髪は送電と
廃熱をしているそうだ。だからあのクリップを外して本体がエネルギー切れになると、
動けなくなってしまう。まぁここは家の中だから外してみたが外では気になっても絶対
にやらないようにしている。
俺はミミが洗面所に入ると入れ替わるように研究室に入る。そしてノリコさんの机に
紙の束を置く。
「ノリコさん、帰ってきてないのかな。……それとも資料を取りに来てすぐ外の研究所
に行っちゃったのかな」
ノリコさんはここ以外にも研究施設を構えている。そこにはノリコさんのスタッフと
ともに何かの研究やらなんやらをしているが俺はミミ以外の研究成果を知らない。この
紙の束を見れば何をやっているか名目上知ることは出来るだろうが、それがどういうこ
となのかは全くわからない。だからノリコさんが何をやっているのかはこの家になじむ
頃には聞かなくなっていた。
「アァァー……ただいまァー……」
ゾンビでも帰ってきたのかと思うような声が玄関から聞こえてくる。ちなみにノリコ
さんはゾンビの研究はしていない、多分。
「おかえりノリコさん」
俺は研究室から玄関に立つノリコさんに挨拶する。
「マドカ、アタシ……ツカレタ……ネル」
ノリコさんはロボットのような片言でゆっくりと倒れ、持っている鞄を枕のようにし
て玄関で寝てしまった。
「ちょっとノリコさん。ベッドまであと少しなんだからそっちで寝なよ」
「ムリ……ツカレタ……イッポモ、ウゴケナイ……」
「子供じゃないんですから、ほら起きて……!」
ノリコさんの背中を揺する。すると芋虫のように背中を丸める。動かないと意思表示
する三十路虫が一匹。
この家に来たばかりの時ノリコさんは、俺の中で尊敬できる大人の枠組みにいた。だ
がそれも俺を迎えてくれた一日目までだった。
俺を迎えに来た日は家を掃除したと言っていたが、ただ物を端に寄せただけなのと研
究室に押し込んだだけという荒業であった。他にも料理をもてなしてくれたが、それは
とても料理に失礼な程のものであった。
あの日は俺の中でノリコさんの株は大暴落した時だったと今でも記憶に新しい。そし
てできないことは諦め、この家ではミミが作る時以外は基本コンビニ弁当なのだ。
「ノリコさん! ノーリーコーさーん!」
「どうしたんですネ? あっ所長、おはようございます!」
髪を整えたミミが洗面所から出てきて丸まっている大きな虫に挨拶する。が、虫の方
は微動だにしない。
「所長……? どうしたんですか?! お腹が痛いのですか?! これは今すぐに百十
七番ですねッ!」
「ミミ、それは時報だよ……」
ミミは険しい顔で受話器を握る。受話器からは虚しく時間を告げるお姉さんの声がし
た。
「ただ疲れて動きたくないんだって。ミミ、一緒にノリコさんを部屋まで運ぶよ」
「うぅ、これは時報でしたか。慌てて応急措置プログラムを読み取ったら間違えてしま
いましたね……」
しょんぼりしながらノリコさんの脇に首をひっかけるミミ。ロボットが読み取り間違
いするのかと突っ込もうと思ったが早く飯を食べたかったからスルーして俺もノリコさ
んの脇に首を引っ掛ける。
「せーのっで持ち上げるぞ。……せーのっ!」
ミミはロボットだが、別にパワーがあるわけではない。むしろ年頃の女の子ぐらいし
かパワーはないのではないのだろうか。前にそこらへんを聞いたら、本気になったら百
万馬力くらいいくかもしれませんですネ! とか息巻いていたが未だ真偽は不明だ。っ
てそれより早くこの大きな虫を寝かして朝食だ。なんでこんな朝から重労働しているん
だろうか。
一階のノリコさんの部屋のベッドに放り込むと、ノリコさんはもぞもぞと掛け布団の
中にもぐりこむ。本当に虫みたいだぞ。
そんなことを思いながら時計を見る。
「飯にすっか」
「はいですね!」
ノリコさんに「おやすみ」といって部屋を出る。するとなんだか焦げ臭い。
「あ、ヤバッ」
俺はオーブンにトーストを入れてあるのを思い出す。ダイヤルもテキトーに回したか
ら今もせっせとパンを焼いている。
俺は慌ててオーブンを開けると中には真っ黒になったパンが二つ。しかし、食べない
わけにもいかないから皿によそってテーブルに並べる。
「な、なんですか……この……エネルギー変換効率の悪そうなモノは……」
「すまん、焦がした……」
ミミは食事からもエネルギー補給が出来る。どのくらい補給できるかはうまいかまず
いかで変わるらしい。色々疑問のある基準だがミミ本人の言っていることだから間違い
はないのだろう、多分。
「もー、マドカは所長じゃないんですからしっかりしてくださいネー」
ミミは頬を膨らまし叱咤する。というかミミもノリコさんのダメっぷりはわかってい
るのか。
「さっきゴタゴタしたからだって、普段はちゃんとできてるだろう?」
「さっきのゴタゴタだってマドカがミミの髪留めを弄らなければすぐに終わりましたで
すネ」
「お前だってヒャクトーバンだーって騒いだじゃないか」
「百十七番ですネ」
「それも間違いだろーが」
「ミミは人間じゃないからちゃんとマドカが教えてくれないとわからないですネ!」
「威張って言うことか! ったく朝から体力つかわせないでくれよ」
このままここにいるとミミに教えてくれとねだられてしまいそうだから俺はパンとサ
ラダを口に放り込み席を立つ。
「ごちそーさま。よーし学校行くぞー」
俺は話を切り上げる気マンマンの棒読みで玄関へと向かう。
「あ、待ってくださいマドカ。まだ話をしたいですネ!」
「なんだそりゃ……。あ、そうだ。ノリコさん起きたら、バナナをあげるんだぞ。じゃ
な」
「あ、はいですね、って待ってください!」
俺はミミの声を無視して玄関を閉めて通学路を走る。それと蛇足だがノリコさんは寝
起きはバナナしか食べないのだ。
俺は家が見えなくなったあたりで走る速度を落として歩く。
ミミは一度教えてモードになるとスッポンのようにしつこい。それに気付いていなか
った頃は馬鹿丁寧にひとつひとつ答えていつの間にか、赤ちゃんはどこからくるの?
とか宇宙の神秘を聞いてきて俺の自我を崩壊させていたものだった。
そんな質問される毎に自分の中の小宇宙を感じるわけにはいかないので教えてモード
になりそうになると俺はミミから逃げるようになっていた。
――すまぬミミ、ゆるせミミ。俺にも答えられないことはある。得意のネットで調べて
くれ。
と思ったがそれもそれで危ない気がしてならない。
そんなことを考えながら歩いていると俺の横を足早に歩いていく同じ学校の女子生徒
が目に入る。こんな時間にめずらしいなと後姿を見ていると、俺はなんだか妙に胸騒ぎ
がしてきた。
そしてその胸騒ぎから一つの疑問が芽吹く。
どこか懐かしい後ろ姿。
「レ、イ……?」
ありえないと思いつつももしかしたらという期待が上ずった声になって漏れる。
俺の声に反応したのか。その女子生徒は振り返り、俺を見る。その容姿は小学生の頃
のレイの面影を感じさせる程だった。
「レイ……?」
と、近づきつつ声を掛けたのと同時に女子生徒も一歩踏み込むと勢いよく俺を壁に叩
きつける。
俺は何かが起きたのか理解する前に背中を強打し肺の中の酸素が一気に搾り出され朦
朧とする。
「その名前をご存知ですの……?」
耳元で囁く声はレイの声、だと思う。
「ご、ご存知だよっ……。忘れるわけないよ」
「どこでその名前をお知りになったのか、教えてもらえますか?」
そういって顔に突きつけてきたのはスタンガン、なのか? クワガタのような先端が
ソレを想像させる。
「レ、レイなんだよね……?!」
「早くその名前をどうして知ったのかお話しなさい。それ以外の言葉にはコレを持って
お答えしますわ」
レイらしき女子生徒はスタンガンを僕の頬にグイグイ食い込ませる。
「小学校の頃! 小学校の頃の友達だったから名前知ってんの! これでいいでし
ょ!? それ、やめてよっ、怖いから!」
「小学校の頃の御友人……ですの?」
女子生徒はスタンガンの先を見せつけたまま、僕からゆっくりと離れる。
「僕が誰だかは……覚えてないの?」
「すみません。ご存知ないですわ。わたくし天才的ですから一度覚えたことはすぐに思
い出せる筈なんですが……」
「そうだ、君の名前は鳳華殿 怜だよね?」
「……えぇ、そうですわ」
「やっぱり、レイだ……!」
「ちょっと……それ以上近づかないでもらえます? コレを食らわしますわよ!」
そう言ってレイはスタンガン? を僕の鼻の穴にぶっ刺してきた。
「ちょ、レイっ、痛いって、なんでこんなことをするの?!」
「あなたが不用意に近づくからですわ」
「わかった! 離れるから!」
そういうとレイはスタンガン? の先をハンカチで拭き取り僕を見る。
「あなたはわたくしの御友人だったらしいのですが、そんなに親しい間柄でしたの?」
「それは、まぁ。お互い初めての友達だったし。僕をいじめられているのを助けてくれ
たし……」
「そうですか、申し訳ないのですがわたくしにはあなたの記憶はありませんですの。わ
たくし急いでいますので、これで失礼します」
そう言ってレイはスタンガンをしまって踵を返して歩いていってしまう。レイからは
明らかに壁を感じて、僕はそれ以上追及することはできなかった。
「あれは……レイだ。けどどうして僕のことを覚えていない……? というかなんで生
きてる……。確かに聞かされた。レイは死んだと……」
あの時の記憶を呼び起こす。
「レイは死んだ筈だ……。じゃあさっきの子は誰なんだ?」
レイが生きている。その響きだけで僕は喜ぶはずなのに、なぜか一抹の不安と気味の
悪さがよぎってしまう。
あの時の、まるで違う世界に来てしまっているような感覚。
同じ制服ってことは……レイも同じ学年だ。でも鳳華殿なんて苗字の子はいなかった
から転校してきたのだろうか?
何か目の前の存在が自分の思っているモノと違う気がして、不安で仕方なかった。
――あれはレイで間違いない。そのはずだ。違うはずがない。
僕は先ほどの女子生徒がレイであることを証明する手掛かりを求めていた。
前のページに戻る/
次のページに進む/
もくじに戻る/