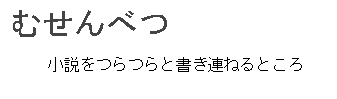かためのこのコ1
前のページに戻る/
次のページに進む/
もくじに戻る/
場所は……研究室。
「ミミ?」
中央の椅子にはミミが座っている。
「……」
返事がない。というか頭を垂れては元の位置に戻り、そしてまた頭を垂れては元の位
置に戻りを繰り返す姿は先ほど感じた雅な雰囲気を前言撤回しなくてはいけない。これ
はただのお寝坊さんのグータラロボットにしか見えなかった。いやロボットとしてこの
挙動はどう評価するべきなんだろうか。
「ミミちゃーん、早く起きないとプラグをさしますよー」
とりあえずグータラロボットを起こそう。そこらへんに横たわっているケーブルを手
繰り寄せる。するとどこかで見たことのあるケーブルだった。
「……!!」
ガタッと椅子からミミが立ち上がる。そしてふらふらとこっちに歩いてくる。
「目ぇ覚めたか? ん?」
その時に俺は気付く。ミミに刺さっているはずのプラグが刺さっていなかった。つま
りそれは。
「お、お腹減ったー……ですネ」
そう呟きながら俺の方へと倒れ込んで来るミミをすぐ横にあった椅子で受け止める。
「お前ちゃんと充電できてないじゃないのか。それにお前硬いんだから転ぶなよ、床が
へこむから」
ミミの充電はちゃんとされておらず、どうやら腹ペコらしい。ミミは椅子にしなだれ
ている。
「一歩も、動けないですネー」
ミミは椅子の上で器用に座り直して体をだらりと仰け反らせ仰向けのまま俺を見る。
「朝食を作りますネ……」
「いや待て。お前その状態で作れないだろ。簡単なものなら俺でも作れるから。それと
面倒くさいからこのまま移動しよう」
ミミが座っている椅子にはコロコロが付いていたため椅子を押してそのままリビング
へと移動した。
ミミ曰くカップ麺は無駄なくエネルギーになるらしく何が食べたいかを聞いたら「カ
ップ麺ですネ!」と即答で返ってきた。
ミミはカップ麺をおいしそうに啜っているがトーストを齧っているこっちとしては朝
からカップ麺のにおいで胃が重くなってくる。
「ふぅーそれなりに満たされましたネ」
ミミはカップ麺の汁を飲み干して満足そうな笑顔を向ける。
「朝からよくそんな重たいものが食べれるな」
「人間は朝に一番エネルギーを補給して夜はエネルギーを補給しないほうがいいんです
よ!」
「そうなのか? 俺は朝はちょろっと食べて、夜はうまいもの食べたいけどなぁ」
「それだと寝ている間にお腹に脂肪がついちゃいますネ」
「ははは、お前は大丈夫だろー」
「むー、そんなことを言われてもミミは気になります。あまり重たくなりたくないです
ネ」
と、他愛のない会話をしていると時計が鳴り八時を告げる。
「え、もうこんな時間なのか? やば、ゆっくりしすぎたな」
かなり早起きしたつもりだったがすぐに出ないとやばい時間になっていた。
「ミミ戸締りよろしくっ」
「あ、待ってくださいネ。ミミも行きますっ」
「ん?」
ミミも学校に行くと言われて違和感を覚える。
「あ、あぁ、早くしろよっ」
が、その違和感はデジャヴを感じたときのように、次に瞬間にはなくなっていた。
俺は玄関で外を見てミミが出てくるのを待つ。外は自動車の音や通勤通学する人たち
の雑音が聞こえる。なのに姿は何一つ見えず妙に周りが静まり返っているように感じた。
「お待たせしましたネ」
ミミは制服に着替えて家から出てくる。髪は結ってあり、いつも通りの格好だ。
「時間がないから走るぞ」
「はいですネっ」
遅刻ギリギリのせいなのか人っ子ひとりいない通学路を俺らは走りなんとかチャイム
が鳴る前に校門を通り抜ける。
「ぜぇ……ぜぇ……。まさか、信号に、一回も引っかからないとは、おかげで、登校マ
ラソン自己新が、出てしまった……」
「ミミもお腹減ってしまいましたネ……」
「朝補給したばかりだろうが……」
「それでもお腹が減る時は減るんです」
他愛のない会話をしながら上履きに履き替える。そして昇降口に向かおうとミミの方
を向くとミミは下駄箱を開けて立ち尽くしている。
「何やってんだ? 早く教室行かないと……って何だコレ?!」
ミミの下駄箱の中は手紙がぎっしり詰まっていた。
「いやーすごい量ですねー」
ミミは手紙の一つをつまみ、俺に渡してくる。俺は手紙を広げその内容に目を通す。
「うわっラブレターか……って俺が見ちゃダメじゃん」
俺は気まずいものを見てしまいミミに突きつけるように返す。
ミミの両手いっぱいに抱えられている手紙。心なしか下駄箱に入っていた時より量が
増えているような……。
「すごい量です! ミミいろんな人からこんなに見てもらえています!」
そう言ってミミは手紙をみせつけ俺を見る。
「そうだなー。こんなに人気があるとは……。でも、お前は誰とも付き合えないだろ?
ほら、早く教室行かないと遅刻するぞ」
ミミはロボットだ。だから人間みたいに誰かと付き合う、なんてことは無理だ。
俺らは教室に駆け込む。担任はまだ着ていない。俺は体を休めるように席に着くとレ
イが俺の横を通り過ぎる。
「レイ、ちょっといい?」
僕が呼び止めるとレイは僕の方を見る。
「なんですの? わたくしちょっと急いでいるので手短にお願いしますわ」
「昨日のことでわかったことがあるんだ。だからちょっと話しがしたいから放課後空い
てる?」
「ごめんなさい、今日は空いてませんの。それでは」
レイはさっさと廊下に出て行ってしまう。
まぁ、用事があるなら仕方ない。改めてまた声を掛ければいい。一限の準備をしてい
るとチャイムが鳴る。
担任が入ってきてホームルームを始める。
「えぇ、今日は特に伝えることはー……ありませんね。皆さん事故のないよう帰ってく
ださいね。以上」
ん? 事故のないよう帰ってください?
「あれ? もう今日の授業終わったのか……?」
俺は自分の机を見ると六限で使った教材が置いてある。待て、普段からあまり授業は
聞いてはいないが、いくらなんでも早すぎる。
「どうしたんですか? ボーっとしてますネ。あ、もしかして授業中居眠りしてたんじ
ゃないんですか?」
「……俺居眠りしてたのか?」
「えぇーと……してましたネ! もうグースカグースカ起こしても起きなかったです
ネ」
「そうか……確かに俺もそんな気がしてきた。昨日疲れてたしな」
俺は立ち上がり大きく腕を振り上げ欠伸をする。
「帰るか。なんだかまだ夢の中みたいで気持ちが悪い」
「ミミはまだ帰れません」
ミミは申し訳なさそうに視線を落とす。
「ん? なんか用事でもあるのか?」
「朝もらった手紙です……それにお返事しに行かなければいけませんネ」
「あぁあのギャグみたいな量の手紙ね。いや、でもお前行く必要ないだろう?」
「どうしてですネ?」
ミミは顔を上げて迫ってくる。今日のこいつはなんだかいつもよりヘンな気がする。
「だってお前……ととと、誰もいないよな?」俺は教室内を見渡すと誰もおらず気味悪
く静まり返っている。「だってお前、ロボットだろ? それにロボットってことは周りに
秘密なんだ。断る理由にロボットだからです! なんて言えないだろうし」
「じゃあミミが、ロボットじゃなかったら、どうなんですか?」
「え? ロボットじゃなかったら? それなら人間なんだから付き合ってもいいんじゃ
ないか?」
「マドカは……」
ミミは先ほどのように再び視線を落とす。
「ミミがどこかに行っても別に気にしないんですネ……」
「どうしたんだよ。今日のお前ヘンだぞ。それにお前はロボットなんだからそんな仮定
の話で落ち込むのはおかしい……ってオイ」
俺はこういうのをアハ体験というのかと実感した瞬間だった。
「ミミ、髪留めバッテリーはどうした?」
俺はミミの髪に触れもう一度確かめる。ミミの髪を結っているのはただの髪留めだっ
た。俺は何かおかしいことになっていると気付きミミの顔に触れ、覗き込む。
「お前……どうやって」
ミミの頬は柔らかく、そして首など関節の接合部分の薄い痕などが見当たらなかった。
「ミミ、人間に成ってみましたネ」
ミミは俺の胸の中に飛び込んでくる。そして俺はそのまま仰向けになるよう倒れこん
でしまうが、それは床に穴を開けてしまうような固めのボディではなく。その、柔らか
めだった、色々と。
「だからこうやっても怪我しないですネ」
「……そうだ、ここはミミの中だ。また俺はサイバーダイブしていることを忘れていた
のか」
俺は体を起こす。
「ミミ、どうして人間の真似なんてした?」
「最近ミミはマドカに全然相手にしてもらえませんでした。ミミはいらない子になって
しまったんでしょうか?」
「そんな訳ないだろう? それにいらないなんて思ってないよ」
「でもマドカ、昨日ミミが晩御飯に何を作ったか覚えていますか?」
「えッ?! えーっと……」
「うぅ……やっぱりミミはいらない子なんですネ。所長のカップ麺と同じなんですネ…
…」
よよよ、と崩れ落ちるミミ。
「そ、そんなことはないぞ! ミミが飯作ってくれることにはいつも感謝してる。それ
にミミをいらないなんて思ったことはないぞっ」
「でも、マドカ昨日何作ったか覚えていませんネ……」
「いや、昨日はちょっと色々あったから疲れちゃってたんだよ。それにいらないとかい
るとかじゃないさ。まぁ今日は話したくないとかそういうことはあると思う。けどだか
らっていなくなって欲しいなんて思ったりはしないよ」
「じゃあミミはいらなくはないんですネ?!」
「あぁもちろんミミはいらない子じゃないよ」
と、言った次の瞬間ミミの髪留めはいつものバッテリーに戻り制服姿はいつものワン
ピース姿にゆっくりと戻っていく。ミミも不思議そうに自分の体を確かめている。
「はぁ……それにしてもどうしていらない子になったなんて悩んでいたんだよ」
「マドカはロボット工学三原則というのを知ってますか?」
「人に危害を加えない、人の言うことを聞く。自分の身は守るってやつだろ?」
「そうですネ。でもミミがいらない子になって捨てられたら三つ目のルールを破ってし
まいますネ」
「あぁだから自分がいらない子かどうか気になっていたのか……ん? 待てよ、でもお
前俺に飛びついてきたりして危害加えようとしてない?」
「そんなことないですネ。あれは愛情表現ってやつですネ」
「いや、待て。お前少し前も俺が冷凍庫に、買って入れたアイス食っただろ」
「そ、そんなことないですネ。あれはマドカの栄養管理を考えてのことですネ!」
「あのアイスは俺のだから食うなよって言っただろうが。なのにお前は黙って食って、
俺にバレたんだろうが」
「そうでしたっけネー……」
「お前全然ルール破ってるじゃんか! あれ、お前本当はいらない子なんじゃないか?」
「そ、そんなことないですね。いらないとかいるとかそういうのじゃないですネー!」
「それは俺がさっき言ったことだろうが……」
「ミミはマドカが帰ってこないと暇ですし、さびしいんですネっ。ミミも学校に行きた
いですネー!」
「それが本音かよ……」
ミミなりに結構悩んでいたことなのだろう。わざわざミミの中の世界を現実世界のよ
うに構築して俺に必要とされているかどうか迫ったのだ。まぁやり方はどうかと思うが。
それに学校を構築できたということはコイツなんどか学校に侵入していたんじゃない
のか?
「学校に行けるように出来るかはノリコさんに聞かないとわからないからあまり俺にだ
だこねるな。それに、そろそろ戻らないとまずくないか? サイバーダイブしてからど
のくらい経った?」
「んー、えーっと四時間とちょっとですね」
「俺がサイバーダイブしたのが六時で、えーっとたしかサイバーダイブしてると時間間
隔が二分の一になるんだよな……じゃあ現実だと八時ってうわっマジに遅刻すんぞ。ほ
ら早く俺を現実に戻せっ」
「ミミも学校に行きたいですネ……」
「わかったわかった、一緒にノリコさんに相談してみよ。それでいいだろう?」
「はいですネ!」
ミミは満面の笑みを浮かべて胸の前で手をポンと叩く。すると俺はまたもや重力を失
い落ちているのか飛んでっているのか分からない浮遊感に見舞われる。
前のページに戻る/
次のページに進む/
もくじに戻る/