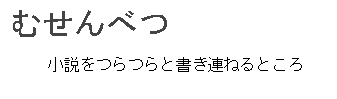2日目3
前のページに戻る/次のページに進む/もくじに戻る/
ミライは家に向かって駆け出した。
なるべく人の多くない道を抜け、家の前の時塔公園が目に入る。そこには違和感のあ
る服装でベンチに座っている大柄な男がいた。
「時塔学園の生徒? なんでこんな時間に公園にいるんだろう?」ミライは自分の格好
を棚に上げ目の端で男を見ているとこちらに気付いたのか立ち上がりこちらに歩いてく
る。
「おめぇ、こんな時間になにやってんだ。まだ学校の時間だろう」男も棚に上げていた。
「偶然だね。あたしも同じことを考えてたんですけど」
「あぁ? ...しまったぁ! 俺も制服じゃねえか!」
ミライは男の言っている意味が分からなかった。
「制服ってことは、学校に行かなくちゃ行けねぇってことじゃねえか!」
「そうだね」
「帰って着替えねぇと!」
「いや、それは違うと思うよ」
「違うのか! 制服だから学校に行かないと行けないんじゃねぇのか?!」
「逆だよ逆」
「学校行くから制服なのか!」
「そうだよ。学生だから制服着て学校に行くんだよ」
「じゃあ、お前はなんなんだ」
「あたしはね、...風邪引いて早退してきたんだよ」
「じゃあ、俺も風邪で早退だ!」
「残念なことに元気な人は早退できないんだよ」
「なに?! じゃあ俺はどうすれば早退できるんだよ!」
「あたしに聞かれても分からないよ」
「があぁぁ...だめだ! ...思いつかねぇ...」男は頭を抱える。
「あきらめて行くしかないね...もう午後の授業も終わるけど」ミライは遠い目で見る。
「じゃあ明日から行くかぁ!」
「もしかしてそう言って昨日もここにいたの?」
「いねーよ! 昨日はまだ停学解けてなかったからな」
「あらま、何やっちゃったの?」
「不良の人に絡まれてよ。ビビッて暴れたら...停学になっていたんだ」
「簡潔すぎて分かりにくいけど、つまり暴力沙汰になったってことなんだね」
「簡単にいえば、そうだってことだ」
「...で、なんで学校に行きたくないの?」
「だってよー...俺の知っている奴はもう誰もいないんだぜ。狼の群れに羊を投げ込むよ
うなもんだぜ...」
「どっちかというと羊の群れに狼投げ込むような感じに見えるんだけど」
「俺が狼に見えんのかよ?!」
「狼って言うより熊かなー...」
「そんな可愛いのか! 俺?!」
「そういう熊じゃないなぁ...って誰もいないってどういうこと?」
「だからよ...卒業間近で停学食らっちまったからよ...留年なんだよ」
「あぁ、それで、誰もいないわけなんだ...。でも、今行かないと、ずるずるずるずる行
かなくなっちゃうんじゃない?」
「そうだよなぁ...。よし! 俺、明日からちゃんと行くぜ!」
男は意気込んで帰って行った。
男は単純で頭は良さそうには見えなかった。
しかし、ミライは男に悪い印象を感じなかった。
一見粗暴そうに見える言葉遣いには気遣いを感じさせない砕けた感じさせる。
ミライは気が合いそうだ、と感じていた。
「そういえば、名前聞いてないや。時塔学園の制服だからジーサンに聞けばわかるか
な?」
ミライは家に帰り、洗濯していた私服に着替え、掃除を済ます。
時計を見ると二時半過ぎだった。
「そろそろ下校時間かな、校門の前で待っているとしますか」
ミライは学校へと向かう。今までは一人の人間のために奉仕し続ける存在だったが、
隠してはいるが人として接している現代がくすぐったく感じ、そしてそれがうれしくも
あった。
未来では、ロボットは人間に近い存在ではあるが人間ではない。人種の壁のように人
間とロボットの間にも壁がある。
それは人種のように対等なものではなく人間と動物のような、悪く言えば一方的な上
下関係にある。
人間の中にはロボットを人間同様に扱う人もいるがやはり同種ではないという事が生
活の中に違和感を生じさせる。ロボットであるミライを一人の少女として扱う時三はそ
の時代からすると変わり者である。独りの男がメスの子犬と付き合っているようなもの
であるからだ。
ロボットからすれば最初から奉仕するという理由が存在しているため人間との扱いの
違いを特に気にしていなかった。ロボットの人権はどうなると問題に取り上げるのも全
て人間の人間による人間だけの問題だった。
時三の場合はミライのために家事をしたり世話をしたりしていた。ミライは最初は戸
惑っていた。自分は使い物にならないから家事を任せられていないと思っていた時期も
あった。
しかし、時三との生活で徐々に変わっていった。奉仕というアイデンティティから飛
び出したのであった。
犬で例えるなら、犬がペットをやめて自分で主人の分の料理を作り、協力する存在
になることだ。
ロボットと人間、お互いが歩み寄ればなれるもう一つのアイデンティティである。
しかし、この歩みよりは世間では奇人変人変態と呼ばれる行為である。
ミライは時三とは対等に付き合っているが、他の人間とは同じ様に付き合えるわけで
はない。
時三もまた、人間から隔離されつつある存在になっていた。
そんなミライは現代に来て認知されていない自分が認められたように感じてしまうの
であった。
校門前で二人を待つ。その姿は恋焦がれる恋人を待つのに近いのかもしれない。
チャイムが最後の授業が終わりを告げる。
ぼやけた意識の奥で規則的な鐘の音が聞こえる。
(チャイムが聞こえる...)
「あ...」
愛はいつの間にか寝てしまっていた。唇からよだれがこぼれそうになる。愛は慌てて
口を押さえ周りを見る。
周りはざわついている。六時限目ということもあり授業はチャイムとともに終わって
いた。
そのためホームルームも気付かず終わっていた。となりには時三はいない。委員会活
動のことを思い出す。
教室は徐々に騒がしさが引いていく。愛が帰る支度を終える頃には部活動がある生徒
等がちらほら残っているだけだった。
愛は教室から階段に向かう。なんとなく廊下から見えるグラウンドに目を向ける。部
活動に励む生徒で溢れている。
階段を下り、玄関に向かう。まだ学校に残ってふざけあっている生徒とすれ違う。
玄関で上履きから履き替える。玄関から校門には生徒で溢れている。
その中に愛を見ている人がいるように感じた。
愛は玄関から出ると。
「あ! 愛! こっち! こっち!」ミライは愛の姿を確認しブンブン手を振っている。
愛は小走りでミライに近づく。
「ミライちゃん...。それは、なんか恥ずかしいよ...」赤面した愛は肩で少し息をする。
ミライがそれを見てニヤニヤしている。
「ミライちゃん...」どういう反応していいいかわからない愛。
「あれ、愛ちゃんのおまけは?」
「おまけって? あ、時三君のこと?」
「正解!」
「お、おまけなんて...時三君より私の方がもっとおまけだよ...」愛は慌ててフォローを
入れる。
「そのフォローじゃ元が無くなっちゃうよ」
「あ...そうだね」
「で、ジーサンはどうしたの?」
「今日委員会活動だから先帰ってくれっだって」
「ジーサンって活動とかやるイメージじゃないんだけど、やるんだね」
「違うの。委員会は絶対なんかしら入らないといけないの。それで時三君ったらこれだ
俺の求める所は!! って入ったら、結構仕事の量が多かったらしくて」
「きっと楽しようとしたから罰が当たったんだね」
ミライは何やってんのと笑い飛ばし、愛はつられて笑う。
「じゃあジーサン置いて先帰ろうか」
二人は学校と時三を背にし歩き出す。
「愛に質問!」
「え、何?」
「時三君とはいつ知り合ったんですか?」インタビュアーがマイクを向けるようにミラ
イは愛の元に手を差し出す。
「え...、と、時三君とは一年の時、席が隣同士で、その時に...です」愛は突然振られて
インタビューの様に答え、愛は一年の時のことを思い出す。
教科書を忘れた時三が話しかけて、そこからなんでもない話をして友達になった。
あの時、時三が教科書を忘れていなかったら愛はどうなっていたのか。そんなことを
ぼんやり考えていた。
「一年の時、隣の席に! それはベタかつ憧れる展開ですね! それでどういう風に仲
良くなられていったんですか?」
「えっと...、最初は時三君が教科書忘れてその時に話すようになって、私、全然友達作
ることが出来なくて...でも、時三君が私に話しかけてくれて、この人は大事にしたいな
って思ったの」
「愛...」
「あ、私なんか変なこと言い出してるね...。ごめんね」
「いや、そんなことないよ。その気持ちは大事だと思う。それでそれで、その後は?」
「普通に休み時間にお話したり、...特別なことは何もしていないよ...」
「んー、普通の積み重ねがきっと、今を作ったんだねー」
「そうなのかな」
愛は今について考える。今はとても幸せだ。時三の他にもミライと仲がよくなり、動
き出すきっかけになった。
「でもどうなの、最近は時三君のことが気になりだしているとか?」
愛はどこかでミライが自分の気持ちに気付いている。根拠はないがそう確信していた。
「...どうなんだろう...。きっと、いや、私、時三君のことが好きなんだと思う」
そして不思議なことに、この女の子には自分の本音が言えてしまう。それが口車に乗
せられているだけなのかは愛本人にもよく分からない。
「おお、言うねぇ。愛ちゃんからそんな告白が聞けるとは」
愛はさっきからとんでもないことを口走っていると思い始め耳が熱くなる。
「...なんだか最近になって不安に思い始めてきたの...。靄がかかったような、漠然とし
た不安が。そうしたらもう、いてもたってもいられなくて...」
「なら、やることは一つじゃないのかな。...ジーサンならきっと心配いらないと思うよ」
「うん...。私が臆病で弱いだけなんだと思う」
「自分を弱いとか思ってちゃだめだよ。そこから自信が無くなっちゃうんだから。それ
に愛は弱くなんかないよ。その一途な思いは強さだと思うよ」
「そうなのかな...」愛は夕日に照らされた赤い空を見上げる。
「うん、びっくりするほどね」ミライはタイムスリップした時のことを思い出し、苦笑
いが出てしまう。
「今は立ち止まらないで前進あるのみだよ! もうそんな怖い顔しないでほら、笑って
笑って」
「こ、こうかな...」愛は頬を引きつらせるように笑みを作る。
「そうそう! そしたらもう屋上でも校舎裏でも体育倉庫でもどこかに呼んで、バシッ
と決めちゃいなよ!」
「ミライちゃんはすごいね...。ミライちゃんと話しているととても落ち着くというか素
直になれるというか、何でも話せる気持ちになるの」
「...あたしだって愛やジーサンといるとなんだか落ち着くもん」
「あ、ありがとう...で、でもなんでだろうね」愛は真剣な表情が崩れて顔いっぱい赤面
する。
「んー、なんでだろうね...」ミライは赤面する愛を見て微笑む。
「私、思うんだけど時三君とミライちゃんは似ている気がするの」
「あたしとジーサンが?」
「うん、なんていうのかな、ずっと一緒にいた人の癖が移っちゃったりする感じってい
うのかな。ミライちゃんと一緒にいるとジーサンと一緒にいるように感じる時があるの」
「あたしとジーサンは似ているのかな? じゃあ愛はあたしのことも好きになっちゃう
のかなぁ?」
「え! あ! ミライちゃんのことも好きだけど! 私は!」
「愛...あたしも愛のことが好きだよ...だから一緒に帰りたかったんだ...」
愛の横顔をミライの吐息がなでる。
「み、ミライちゃん...!」愛は真っ赤になり固まる。
ミライは愛に近づく。愛は後ずさる。
ミライは追い込むようにゆっくり曲がり角に愛を誘導する。
「何やってんの...」
不意にミライの後ろから声が聞こえた。ミライはゆっくり振り向く。
「あれ、ジーサン早かったね。もっとゆっくりしてて良かったのに」
ミライは口元をニヤリと歪める。
「あんまり、愛をからかっちゃだめだよ」
「いえいえ、からかってなんか。あたしは愛のこと好きだもん。愛は?」
「え! わ、私もミライちゃんのこと、好きかな...って何言ってんだろ私、あの、この
好きって言うのは友達としてであってその、変な意味じゃなくて!」
「もうその辺にしといてあげなよ、愛がパンク寸前だから...」
「うん、愛、大丈夫?」
「えっと! 私は! その...とっても大丈夫!」
「ダメっぽいね...ジーサン」
「お前が壊したんだからお前が直せよ...」
「愛、大丈夫? ちょっとふざけすぎたかも...」
三人はそれぞれの帰路につく別れ道で一度足を止める。
「愛、大丈夫? 落ち着いた?」
「うん、大丈夫だよ、私も時三君としか話していないからダメなのかもね」
「いや、こいつはかなり特殊だから気にすることないよ」
「ありがとう、時三君、ミライちゃん、それじゃあ、また明日」
じゃあねと別れ愛は二人に背を向け歩く。
前のページに戻る/次のページに進む/もくじに戻る/