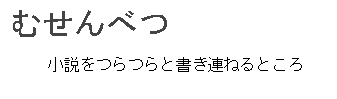1日目3
前のページに戻る/次のページに進む/もくじに戻る/
マナちゃんは糸が切れた操り人形のように椅子から崩れ落ちそうになる。それをマホち
ゃんが慌てて支える。
「マホちゃん、ナイスフォロー。ケン君、どのくらい経った?」
「先生がマナを見つめだして、三十秒くらいです」
現実世界と精神世界では時間の進み方は違う。ボクは結局マナちゃんの中学と高校の記
憶を全て辿った。それは三年と一年一ヶ月分の時間を三十秒で経験したことになる。なん
というか、老けた気がする。
「それで、マナの「問題」分かったんですか?」
「あぁ、分かった。後で作戦会議といこうか。ケン君今日はバイトあるの?」
「今日は……無いですね」
「じゃあ、君の家に後で行くよ」
「分かりました」
「それと、マホちゃん。ちょっといいかい?」
マホちゃんは意識を失ったマナちゃんを椅子から落ちないように支えていたがいつの間
にか、お姫様抱っこしていた。
「先生! マナを保健室に連れて行きます!」
「うれしそうに言わないの。……あぁちょうどいいや。もう一人協力して欲しい人がいる
からボクも一緒に保健室に行こう」
保健室の中はいつも薬品の匂いがする。この匂いを嗅ぐとなぜか、安心してしまう。
「すみません、フックンにちょっと頼みたいことがあるのですが…」
「あらッ…、どうしたのかしらッ…林道先生ッ…?」
いつも保健室の奥の事務室で荷物の整理をしている保健室の先生。みんなからフックン
と呼ばれている。ちなみに事務室は名前だけでフックンの物置となっている。そして、事
務室の半開きのドアの向こうからフックンの声がする。なんだかいつも通りの対応だが、
声に力がこもっている。何かと戦っているのだろうか。
「フックン先生、ベッド借りていいですか!」
マホちゃんがそう言いながらマナちゃんをベッドに寝かせ、靴を脱がし、ブレザーをハ
ンガーに掛ける。その手馴れた動きから優しいお姉さんというより犯罪の香りがした。そ
してハァハァ言いながら鼻息荒くベッドに寝かせていることは突っ込まないでおく。
「えぇ、どうぞッ…。……すみませんリンドウ先生ッ…ちょっと先にワタシのお願いを良
いですかッ…」
力のこもった声を出している事務室の中を覗く。
「あぁ、また溜め込んで…。いつも整理してるのになんでこんなになってるんですか…」
所狭しとダンボールが事務室の中を占領している。そしてフックンは山積みになってい
るダンボールを両手を突き出しぺたんこ座りをして支えていた。
「すみませんッ…。落ちてきそうなのを助けてくださいッ…」
フックンは視線をダンボールの崩れそうな一番上の部分に向ける。確かに今にもフック
ンの顔面めがけて落ちてきそうだ。
「これ降ろしちゃいますよ。こんなに高く積むから崩れるんじゃないんですか?」
フックンの横から一番上のダンボールを持ち上げる。中には使い古したノートがいくつ
も入っていた、そして普段使わない腕がダンボールの重さに悲鳴をあげる。そしてダンボ
ールが徐々に重力に従いボクの腕からすべり落ちそうになる。
「フックンッ…。どいてくださいッ。ちょっとこれボクには重いですッ…」
自然と言葉に力がこもってしまう。フックンはフックンでボクが持ち上げたダンボール
の下の段以降を両手で支えていたがボクが持つダンボールに後頭部を押しつぶされ伏せる
形になっていた。
「林道先生ッ…すみませんッ…。もう一段ッ、もう一段降ろしていただければッ…」
「ちょッ…! ケン君ッ! ケン君ッ! ちょっと来てくれッ!」
「さっきからすごい力のこもった声出して、何と戦ってるんすか…ってうわっ…」
ケン君が事務室の中を覗きたじろぐ。
「これッ…僕が持ってるダンボールッ、持ってッ…」
ケン君は慌てて僕の持つダンボールに腕を潜り込ます。ボクはフックンが押さえている
ダンボールを持ち上げてすぐさま床に落とすように置く。ダンボールからは重く低い音が
床に響き中身の重さを感じさせる。
「ふぅー。ありがとうございますリンドウ先生。それにケン君もね」
フックンは座ったままの体勢でこちらに振り向き照れ笑いをする。
「あのー、このダンボール何が入っているんですか?」
ケン君はダンボールの中を覗きこむ、ボクもつられて中に目を向ける。
「主にワタシの私物でしてー…。見てもあんまり面白いものじゃないですよ」
中には使い古した大学ノートが何十冊も入っていた。表紙には使っていた期間とフック
ンの名前が書き込まれてあった。
「あ、あとはワタシが片付けときますので。それでリンドウ先生の用事ってなんですか?」
「あっえーっとですね。また生徒さんを保健室に連れてくることが多くなると思いますの
でってことを言いにきたのです」
「さっそく、連れて来ているのね。いいですよ。使っても構いませんよ」
ボクはフックンにありがとうございますと一礼して事務室から出る。ケン君はフックン
のダンボールを片付けるのを手伝わされる。渋々引き受けているように見えるが彼は人に
言われると断れない性質である。それが良い所であり悪い所であるが。
もう一人は放っておくとマナちゃんに手を出しそうな雰囲気があるので仕切りに遮られ
たベッドの中に声をかける。
「マホちゃん、マナちゃんは起きた?」
返事はない。何度か声をかけてみるがやはり返事はない。
「開けるよ?」
最後にもう一度聞くが返事はない。寝てしまっているのだろうか。仕切りに手を掛けた
瞬間。仕切りの向こうで影が一つ起き上がる。中を見るとマナちゃんが体を起こしてキョ
ロキョロ周りを見ていた。そしてボクを見つけ視線を止める。
「調子は大丈夫かい?」
「……」
無視された。タイミングを計ったように視線を逸らされる。まぁまだマナちゃんの記憶
を覗いただけで何も施していない為、期待はしていなかったが無視されると少し悲しくな
る。ちなみにマホちゃんはマナちゃんに添い寝をするように涎を垂らし寝ていた。そのマ
ホちゃんをマナちゃんがベッドからどかそうとするが、小さな体にはもちろん力は備わっ
てはおらず、マホちゃんはビクともしない。
「マナちゃん、そこで寝ている子は君と友達になりたいと言っていたんだけど、友達にな
ってあげてくれないかな?」
この子の記憶の中を覗いてまず感じたことは友達はおらず、日常の殆どを兄と過ごして
いたことだ。その兄がいなくなって人との接し方が分からないのだろう。決して何か深刻
な理由があって話せないわけじゃない、きっと話し方が分からないのだろう。だから、友
達を作らせる。
「どうかな、そこで寝てる子は君が大好きすぎて仕方ないんだ」
反応は無い。こうやって色んなことを流してきてしまったのだろう。だが、ここでまた
流してしまっては意味が無い。ボクの「力」を使って返事をさせても意味が無い。だが、
この子は俯きも視線を外したりもしない。ただ遠くを見て反応しない。
「んー。仕方ない。そうやってだんまりを決め込むというなら…」
ボクは保健室の机からティッシュを持ってきて紙縒りを作りマホちゃんが寝ている側に
回りこむ。そしてマホちゃんの鼻に紙縒りを突っ込み突っつく。数秒してマホちゃんの顔
が歪み大きなくしゃみをする。マホちゃんはのそのそと目を覚まし目を擦りながらマナち
ゃんを探す。
どうやら、マホちゃんのスキンシップに本能的に危険を感じたのかマナちゃんはそそく
さとベッドから飛び降り革靴を履いてハンガーに掛かったブレザーを取ろうと両手を一杯
に伸ばす。
そこで、マナちゃんの両脇に蛇のように両手を伸ばすマホちゃん。マナちゃんはバンザ
イをする格好で固まる。その光景は弱肉強食の世界を彷彿とさせる。小動物に狙いを定め
る獰猛な動物。それは食すためか愛でるためかの違いしかなかった。
「マホちゃんストップ」
ボクの声に反応して犯罪的に動く指を止めマホちゃんはゆっくりと振り返る。
「あれ、先生…。いつからそこに…?」
「君を起こしたのボクなんだけど、とりあえず鼻に引っかかってる紙縒りを取りなよ」
「えっ?! あっ、あぁすみません…」
マホちゃんはマナちゃんから手を離し紙縒りを取り、小さくくしゃみをする。…さきほ
どのくしゃみを見た後だとなんともいえない気分になる。
「マナちゃんも起きた事だし、そろそろ帰りなよ。三人でね」
ブレザーを羽織ながら保健室から出て行こうとするマナちゃんの肩を掴む。少しずつ慣
れていってもらわないとね。片づけを終えて戻ってきたケン君を確認し、マホちゃんにそ
ろそろ起きるよう促す。そしてケン君の家に集合する旨を伝える。
「分かりました。マナも連れて行きます?」
「いや、マナちゃんは連れてこなくていいよ。でも、これからは三人で帰宅するようにね。
学校でもなるべくマナちゃんに声かけてあげてよ」
「んー。今までも声かけていたんですけど無視されちゃうんですよねー…」
ボクの横を通り過ぎてドアの近くで止まって振り返る。マホちゃんは苦笑いを浮かべな
がら頭をかいて弱気なことを言う。
「大丈夫だよ。どう接していいかわからないだけだから。さっもうお帰り」
マナちゃんの肩を離す。マホちゃんの横を歩き仲の良い友達に……は見えなかった。だ
って、マナちゃん不自然に距離開けてるし。頑張ってねマホちゃん。
「先生、片付け終わりましたよー」
「あっお疲れ様、二人とも先行っちゃったよ」
「えっまじっすか!?」
ケン君は端に置いてある鞄を掴み慌てて二人を追いかけようとする。
「ケン君これあげるよ」
ボクが投げたものをケン君は反射的にキャッチし手の中を確認する。手の中の缶ジュー
スとボクを交互に見る。
「今回、君たち二人に頼ることになると思うから、よろしくね」
「これじゃあ足りないっすよ。今度何か奢って下さいね」
悪戯な笑いを浮かべるケン君。君はいつも元気だね。
「はは、じゃあそれは頭金だと思ってくれ」
いただきます、と言ってケン君は保健室から駆け出していった。彼らならマナちゃんの
心をきっと開いてくれる。
「今度はケン君とマホちゃんと何するんですか?」
小学生の相手をしてあげるような優しい笑顔でフックンが聞いてくる。この人はなんて
いうか年齢の割りに考えが子供っぽい。まぁそんな子供っぽさも長所に変えてしまうほど
の容姿の持ち主である。この人何歳なんだろうか…。聞かないでおこう。
「ただの悩み相談ですよ。二人には先生に言えない悩みを聞いてもらう係りです」
「なーるーほーどーねぇ。ケン君は明るくて人当たりいいもんねぇ。マホちゃんは誰にで
も分け隔てなく接するけど女子の悩みなんて聞けるの?」
「んー。だからケン君と一緒にいつも行動するように言ってるんだけどね。二人が付き合
っているっていう印象与えとけば面倒な問題も起きないだろうし。学校にいる間はずっと
一緒だから陰湿なこともされないと思います」
「ふふー。そう簡単にいくのかしらねぇ」
「簡単にはいかないと思いますけど、あの二人がいるのはZ組です。陰湿だろうがなんだ
ろうがぶっ飛んだことをされると思います。でも、Z組の生徒は友達を作ることをしませ
ん。だから普通の生徒のような問題は起きないと思っているんですよね」
「そうかもねー。それにケン君よりカッコいい男子もいるし、マホちゃんよりかわいい女
の子もいるしねー」
「まぁ見た目はそうかもしれないですけど、ボクはみんなが何を考えているかが全然沸か
なくて不気味ですよ…。ケン君とマホちゃんは嘘をつけない性質ですからいつも顔にでて
ます。でもボクはそんな二人の方が好きですね」
「あららー、いい先生といい生徒ですね」
「いい先生なんかじゃないですよ。正直他のZ組の生徒は不気味です。なんでそんな思考
に至るのだろうかって事を思う時ありますし」
「そんなもんなんじゃないんですか? そこを指摘して生徒は成長していくんですよ。き
っと!」
「そんな握りこぶしを作って力説されるとはフックンも生徒の相談とかよく乗ってあげて
たんじゃないんですか?」
「まっさかー。ワタシの方が乗って欲しいくらいですよー。ワタシもリンドウ先生に相談
乗ってもらおうかしら」
「ははは……。先生の相談だったらいつでも受けますよ」
「あら、生徒はどうするの?」
「ケン君とマホちゃんにも大人の苦労を聞かせてあげればいいじゃないですか」
「これはご丁寧に。でも大丈夫よ。ワタシはいつだって元気元気ですから!」
右腕にグッと力を入れて力瘤を作る素振りをする。ボクは苦笑いを浮かべ時計を見る。
「それじゃあ、いつまでもここに居られませんので、お邪魔しました」
「またね、いつでもいらっしゃいな」
保健室を後にして職員室に戻る。今日の仕事を片づけ明日の準備をする。
「Z組だけ小テスト難しくしても平気で時そうだなぁ…」
明日の漢字テストのプリントに視線を落とし小さく呟いてしまう。印刷室でプリントを
刷る。印刷機が頑張っている間、暇なためボーっとグラウンドの方を見る。外は野球部や
ラグビー部、サッカー部などが走り回っている。三種の部が使っていても余るほどこの学
校のグラウンドは広い。が、ボクがそれを有効活用できることは特にない。暇だから眺め
ていただけで、動いているものを反射的に見てしまっただけだ。遠くで動き回る生徒を見
ていると、手前に何か挙動不審な影が見える。何かを窺っているのか、怯えているのか挙
動不審すぎて、異様に目立つ。なんとなくその陰に近付くと、ボクに気付いたのか走って
行ってしまった。
今のはZ組の生徒だった。名前は鹿羽剛士。名前とは真逆な印象な生徒だ。色白で線の
細い生徒だ。特に誰かとしゃべっている訳でもなくいつも、周りを窺っているか伏せてい
るかのどっちかしか見たことない。だが、勉強はできるようで小テストでは全科目平均し
て成績が良い。どこにでもいそうな感じの生徒だが一体、どんな「問題」を抱えているの
だろうか。
前のページに戻る/次のページに進む/もくじに戻る/