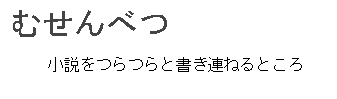1日目4
前のページに戻る/次のページに進む/もくじに戻る/
「っとまずはマナちゃんからだ。あの子はマホちゃんに任せよう。まずは同性のお友達か
らだ。ケン君は案外シャイだからなぁ。仲良くなれば面白いんだけどねぇ。マホちゃんと
マナちゃんが仲良しに。次にケン君。そうすればマナちゃんも普通の学生生活を送れるだ
ろう」
一度伸びをし印刷室に戻る。優秀な印刷機は仕事が終わったことをランプで示す。
職員室に戻りプリントの山をしまう。さて、もう一仕事だ。学校を後にし、ケン君の住む
アパートに向かう。彼は去年両親が他界しており独り暮らしをしている。元々は一軒屋に
住んでいたが親戚との相続問題を嫌って家を譲ったとのこと。しかし、あまりこの話を掘
り下げても意味はない。
ケン君のアパートに着く。階段を上り二階の一番端の部屋のドアをノックする。すぐに
ドアが開きケン君が顔を覗かせる。
「待ってましたよ。晩飯がもうすぐ出来るんで入ってください」
中からは食欲をそそる匂いがもれ出てくる。ボクは甘い香りに誘われるように上がりこ
む。
「あ、先生ちょうどいいタイミング! もうできるので座って待っててください」
マホちゃんがエプロン姿でフライパンと菜箸を使って何かを料理している。ボクは自炊
派ではないので何をどう作っているかは説明できない。
「手洗って来るよ」
洗面所で手を洗う。マホちゃんはたまにケン君の家に来て料理を作っている。マホちゃ
んの家は両親共働きで一人の時が多い。ケン君も料理を作れないことはないが一人で食べ
るより二人の方がいいとの事でケン君の家で晩御飯を作って食べている。ここまで仲が良
いと付き合っているように見えるが二人は別に付き合っているわけじゃない。ただの幼馴
染である。二人の親も仲が良く、家族ぐるみで旅行にも行っていた。二人の関係はどっち
かというと恋人というより家族なのだろう。そこら辺の線引きは二人のことだからあまり
知ろうとは思わない。まぁ、二人にはずっと仲良しでいて欲しいとは思う。
「先生できましたよー」
マホちゃんの声がし、三人が腰を下ろすと狭い部屋で食卓を囲う。
「こうやって食べるとなんか家族みたいですよね!」
マホちゃんがご飯を装いながら言う。
「ふふ、じゃあボクはお父さんでマホちゃんが若妻だね。ケン君は離婚したお母さんの子
だ」
「えっ! なんすか、その無駄に重い設定は」
「で、マホちゃんは二人目」
「リンドウ先生はまず結婚すら出来そうもないですよねー」
「んー普通に酷いこと言うね。この若妻さんは。ほら不良息子なんか言ってやれ」
「同い年なのに息子と母親ってすごい関係っすよね。タメ口聞いていいのかどうか…」
「不良息子が照れてるよー。お母さんに甘えてもいいんだぞー」
「ケン君はマザコンだったのか…」
「いや、マザコンでもないし、甘えもしないっすよ」
「じゃあ、君は、マナちゃんみたいなのが趣味だということか」
「二択なんすか…」
「いやそこに、男も入れていいけど、それを選ぶというなら今後の付き合い方を考えさせ
られるんだけど」
「じゃあ、マホ派でいいっす」
「お、普通に照れること言うじゃない。お母さん照れちゃうよー」
「消去法だよ。男は論外だし、マナ派は世間的にアウトだろーよ…」
「ケン君それはずるい言い方だよ。まるで世間のせいにしているけど、周りなんて気にし
ないで君の趣向で生きてみなよ!」
「先生、口からご飯粒飛んでいるっすよ」
「じゃあ、あたしはマナ派で」
「えっマホちゃんはそこでアウトロー路線に行くのかい…。しかも地味にケン君かわされ
たね」
「べ、別になんとも思ってないっすよ!」
ケン君は複雑そうな顔をしてご飯を口に流し込む。ケン君は割りと弄りやすい。が、マ
ホちゃんは平気でヘンなことを言う。いや、平気では言ってないか。人一倍傷つきやすい
からああいう風にふざけてしまう。どこまで本気か、どこまで冗談かを測らせない。
そしてマナちゃんは人と接したことがないから人の気持ちが分からない。マホちゃんと
マナちゃんの組み合わせは大丈夫だろうか。
「先生、作戦会議ってマナのことでですか?」
マホちゃん僕の考えを見抜くように話を切り出す。するとケン君も我関せずとご飯を食
べていた手を止めてボクを見る。
「マナの「問題」ってなんだったんっすか?」
二人は食事の手を止めボクを見る。
「まぁ、とりあえずご飯食べてからね」
食器を片付け終え食卓には湯飲みが三つ。お茶を一口含み飲み込む。
「それじゃあ、これからマナちゃんの「問題」について話すよ」
二人は正座して少し前かがみでボクを見る。そんなに気張らなくてもいいのに。
「マナちゃんは、友達を作ったことがない。そして極度の人見知りとノミ以下の心臓、つ
まり極度のビビリで人と話すのが怖いんだ」
「なんすか、それ?!」
「もしかしてしゃべれない理由って……友達と話したことが無くて怖くてしゃべれないん
ですか?!」
それだけです。
「でも、お兄さんとは良くしゃべっていたよ。それはもう絵に描いたような仲の良い兄妹
だ。でもそれだけなんだ。お兄さんのリョウ君とは親が離婚して離れ離れになったんだ。
離れ離れになってからは全く一言も発していないね」
「よく、生活できてましたね。大変だったんじゃないでしょうか…」
「母親が働きっぱなしでマナちゃんは家で一人でご飯食べていたからね。でもいい子だっ
たよ。学校で問題も特に無く、母親のために晩御飯作っておいたり家事をこなしてたし」
「それって「問題」あるんすかね…」
「大有りだよ。確かに成績も中の上、家事をさせれば何でもこなすけどあの子の「問題」
は圧倒的にコミュニケーション能力が劣っていることだよ。赤ちゃんレベルだったね。い
や赤ちゃんより下かもしれない」
「それ、言い過ぎじゃないんですか…」
「マホちゃん…。これが言いすぎじゃないからZ組なんだよ。知識はちゃんと高校生だけ
ど、マナちゃんは会話が出来ない。もし何か問題起こしたりした時、彼女は何も出来ない。
なぜなら会話が出来ない。前にも後ろにも進めない。そんな子が親の元を離れて社会に出
てみろ。使いものにならないよ」
二人は、困惑の色を顔に滲ませる。その気持ちは分かる。ボクだって意味が分からない。
兄がいなくなったから誰ともしゃべらなかった。何だそれは。
しかし、マナちゃんの記憶を辿ったところ、それ以外考えられない。別に母親とも関係
は良好だった。これは客観的な意見じゃない。マナちゃんから見たこの世界をボクは覗い
てきたからだ。心に病を抱えるようなことは何もなかった。イジメも、恋愛も、会話も、
何もなかった。
「まぁでも、体とコミュ力以外は知識高校生なんだ。少しずつ会話が出来るようになれば
あっという間に話せるようになると思うんだ」
「なんだか、普通に接していいんっすかね」
「あぁ、それは問題ないと思う。むしろ、普通に接してあげて。最初は無視されているよ
うに感じるかもしれないけど、表現の仕方が分からないだけだから」
「動物みたいっすね」
「マナはあたし達と一緒なんだから…動物みたいなんて言わないでよ」
「おっ、マホちゃんやる気あるねぇ」
マホちゃんは少し不安そうな表情を浮かべる。マナちゃんの家庭環境に感じるものがあ
ったのかも知れない。マホちゃんもお父さんは出張で家にはあまりいない。お母さんも看
護師で夜勤などもあり、家にいないこともある。一人で家にいる寂しさに共感しているの
かもしれない。
逆にケン君は結構ドライなところがある。両親の死はすぐに受け入れていた。むしろそ
の後の親戚との相続のことの方が参ったとのことだ。だが、ケン君のそのドライな部分は
マホちゃんとは相性が良かったりする。マホちゃんは結構大事に考えてしまう性質だ。ケ
ン君が事故にあった時も泣きながら真っ白な死に装束で病院に来たらしい。さすがマホち
ゃん。突っ込みどころ満載で、なんか違う方向にぶっ飛んでいる。
「マナちゃんはマホちゃんに任せた方が良さそうだね。ケン君はとりあえずおとなしくし
ててよ。君が話しかけると多分、ビビッて前に進まなそうだ」
「分かりました。マホ、ほらこれやるよ」
ケン君はボクが渡した缶ジュースをマホちゃんに渡す。マホちゃんは困惑したままケン
君を見る。
「リンドウ先生からの頭金だよ。マナをしゃべれるようにしてリンドウ先生に今度何か奢
ってもらおうぜ」
ケン君は笑いながらマホちゃんを見る。マホちゃんもつられて薄く笑う。相変わらずの
凸凹コンビっぷりを発揮された。
ケン君の家を後にしマホちゃんと帰り道を歩く。晩御飯を食べて話し合いをしていたた
め外はもう暗く、表通りまでマホちゃんと歩く。
「どう、マナちゃんのこと、不安なのかい?」
先ほどマナちゃんの話せない理由をケン君と話している時ずっと不安そうにマホちゃん
は聞いていた。この子は相変わらず心配性だ。昔ほどではないが今でも周りの人が傷つく
とそのぶっ飛び方は変わらない。
「恐るべき、Z組…」
「何か言いました?」
「いや、何も」
「リンドウ先生、マナって何か趣味ってないんですか?」
「ん、そうだねー…」
「もしかしてあの子、何も無いんですか?」
「そうなんだよねぇ…。本当に何も無いんだ。多分言われたことだけをやってきたのだろ
う」
「どうして、お兄さん以外とは話さなかったんでしょうか?」
「お兄さんは色んなことを知っていた。同級生の友達と一緒にいるより世界は広く、色ん
なものが満ちていた」
「だから、お兄さんといつも一緒にいたんですか?」
「そうだね、お兄さんが家を出て行く時もマナちゃんにお母さんを助けてあげるよう色々
教えていたね。マナちゃんはそれを実践しているんだ。掃除、洗濯、料理、勉強等等」
「なんだか、本当に極端な生活ですね…。家事をするけど全く話さなかったって事はずっ
と独りだったってことじゃないですか…」
「マホちゃんはマナちゃんがずっと独りだったことが悲しいことや不幸だと思うかい?」
「それは…分かりません。あたしだったら寂しいと思いますけど…。ケンみたいに独りで
も別にっていう人もいます。けど、友達とかいれば、もっともっと広い世界があるんじゃ
ないでしょうか。ケンだって料理を作ることは出来ます。けどあたしがわざわざ作りに行
って、二人で食べる。こういうことには独りじゃ分からないものがたくさんあるんじゃな
いでしょうか」
「そうだね。マナちゃんはお兄さんからしかそういうものを享受して来なかった。もっと
いろんな人と触れ合って色んなものを感じればあんな状態にならなかったかもしれない
ね」
「よっぽどお兄さんの存在が大きかったんですね。そういえば、マナのお兄さんってどん
な人だったんですか?」
「ふふ、マナちゃんからはとっても格好良くて頼りになる存在だったらしい。もう、この
人がいれば他は何もいらないって感じだったね」
「うーん、あたしって一人っ子なんで兄妹の関係っていうのがいまいち分かりませんがそ
こまで頼りに出来る存在なんですかね」
「それは家庭の環境とかによって違うんじゃないかなぁ。兄が高圧的な家庭もあれば献身
的なのもいるだろう。マナちゃんからは高圧的だけど頼りになるっていう兄だったみたい
だし」
「あたしもそんな風に接すればすぐに打ち解けること出来るんでしょうか」
「いや、いつものマホちゃんらしく接すればいいと思うよ。最初は戸惑うことも多いと思
うけどお兄さんとは違う世界を見せてあげないとね」
「あたしらしく、ですか。ってことはふにふにしている所を重点的に責めろってことです
ね!」
「あぁ、まぁ、それもマホちゃんらしいところだからいいと思うよ…。多分」
表通りに出る。まだ人気が多く賑わいが見られる八時過ぎ。あまり制服姿では歩いて欲
しくない時間だ。
「それじゃ、寄り道しちゃダメだよ」
「もうしちゃったので後は真っ直ぐ帰るだけです。それじゃ失礼します!」
マホちゃんは人ごみの中に飛び込んでいく。その背中は人ごみに混ざり見えなくなる。
マホちゃんが見えなくなりなんとなく街を見渡しボクも家路に着く。
前のページに戻る/次のページに進む/もくじに戻る/