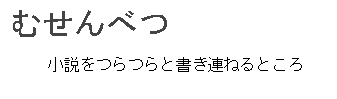2日目1
前のページに戻る/次のページに進む/もくじに戻る/
二日目の昼休み、マナちゃんの様子はどんなもんかとケン君にメールを出してみる。
―――相変わらず反応が無いです。マホもギクシャクしながらも話しかけています。
話しかけて反応がないと不快に思うだろう。特にマホちゃんなんかへこむだろう。
「マホちゃんには大変なことをお願いしちゃったかなぁ…。」
ケン君にはマホちゃんがダウンしたらマナちゃんの相手をするようメールした。
六時限目の授業が終わり、Z組に向かう。Z組からは生徒の話し声が聞こえる。
しかし、ドアを開けると狙ったこのようにシンと静まり返り皆自分の席に着席して待っ
ている。なんだろうか、この謎の団結力。
しかし、一人だけ伏せていた生徒がいる。マホちゃんだ。マナちゃんに無視され相当へ
こんでいるようだ。隣の席のマナちゃんはいつも通り。今日は校訓を眺めている。
「えー、特に連絡は無いので、これで解散。日直」
日直が号令をかけて生徒は着席する。あぁ僕が出て行かないとこの子ら解散しないんだ
った。職員室に戻り、教室に行っても大丈夫かケン君にメールする。
―――大丈夫です。あとマホはダウンしました。
簡単で伝わりやすい文章が送られてくる。ケータイをポケットにしまい早足にZ組に向
かう。
Z組にはケン君たち三人以外は生徒はいなかった。ケン君はぼーっと校訓を眺めている
マナちゃんの前で何かやっている。
「いいかマナ。よーく見てろよ」
そう言って右手と左手をマナちゃんの前に掲げる。右手には五百円玉が一枚。左手には
何も入っていない。
「そいっ!」ケン君は両手を閉じ一瞬右手と左手を交差させる。そして手を開くと右手に
は五百円玉はなく、左手に、五百円玉は無かった。
そして遅れて、小銭が転がる音がする。
「今どこで音がした?! おい、マナ今見てなかったか?! おい?!」
ケン君は教室の端の方に這いつくばって五百円玉を探し出す。ボクはとりあえずマナち
ゃんの方を優先した。
「やぁ、マナちゃん。ちゃんと仲良くやっているかい?」
反応はなしと。これに話しかけ続けるのはしんどい。どうしたもんか。マホちゃんは机
に伏せたままだ。
「マホちゃーん。大丈夫?」
「ダメ…です…」
顔を見なくてもどんな風になっているか想像できる抑揚の無い声で返事を返してくる。
「どう? マナちゃんと何したの?」
「昨日は何食べたのかとか、何が好きなのかとか、あたしの話をしたりとか、マナのほっ
ぺ触ったりとか、マナのお腹触ったりとか、マナのおっぱい触ったりとか」
「うん後半はダメだね、特に最後。それで、相手にしてもらえたの?」
「ダメでした…おっぱい触っても、ピクリとも反応しませんでした…」
「いや…そういうことはしなくていいから」
「それじゃあ、あたしじゃありません…。あたしはおっぱいを揉みたいんです!」
顔を上げ立ち上がるマホちゃん。目の周りが真っ赤になっている。もしかして泣いてい
たのだろうか。マホちゃんはマナちゃんの前の席を引っ張り出し、背もたれに抱きつくよ
うに座る。そしてマナちゃんとにらめっこをするように顔を近づける。
「…」「…」
お互い、だんまりしたままにらみ合う。いや、睨んでいるのはマホちゃんだけだ。端の
方でケン君が動いているだけで二人はじっと止まっている。
じっと固まっている二人。痺れを切らしたのかマホちゃんが睨んだままマナちゃんの顔
に手を伸ばす。
頬に手を伸ばし、掴む。掴んだ頬を、引っ張る。マナちゃんの顔は歪み思わず吹き出し
そうになるが我慢せねば、笑ったらなんか悪い。表情が緩むのを左手で隠しながらマホち
ゃんとマナちゃんを見守る。というかマホちゃんの行動に意味があるのだろうか。
「先生今日は帰ります!」
マホちゃんが立ち上がり真剣な顔でボクを見る。そして、マナちゃんの後ろに回り込み
脇から抱き上げ立たせる。そして、マナちゃんの手を握る。その光景は姉と妹というより、
変質者につれて行かれる幼女に見えた。多分マホちゃんがハァハァ言っているからだろう
が突っ込まない。黙っているれば可愛いと思うのに、そこはZ組だからなのだろうか。
「あまり過激なことはしないようにね」
「大丈夫です! ちょっとうちに連れて行くだけですから!」
一抹の不安を感じさせるが、とりあえずマホちゃんに任せよう。
「それでは失礼します! いこ、マナ!」
変質者の後ろについていく幼女の図が完成していた。ボクは二人の背中を見送る。なん
だかんだ言って意思疎通が出来ているのかも知れない。…一方通行だけど。
そして未だに五百円玉の消息が掴めずロッカーと壁の隙間に手を伸ばすケン君に話しか
ける。
「ケン君、ちょっといい?」
「今忙しいっす…。後にしてくれませんか…」
這いつくばって探すその背中と震える声が壁に押しつぶされた蛙みたいで悲壮感を漂わ
せる。
「この五百円玉は今日の晩飯なんです…これが無いと…」
「ほら、これ、さっきボクが教室に入ったときに拾ったよ」
「えっ…」
ケン君は立ち上がり埃まみれの制服を叩く。
「先生、ありがとうございます」と言ってボクの手の中の五百円玉に手を伸ばす。ボクは
避ける様に手を引くと、ケン君は驚いたような顔をしてボクを見る。
「五百円玉を見つけた代わりにちょっとそこまで付き合ってよ」
ケン君の返事を聞かずに歩き出す。
そして、印刷室とグラウンド前の自動販売機の前で止まる。
「先生、どこいくんすか?」
ケン君は困惑しボクに聞いてくる。ボクはは無言で自販機にお金を入れいつも飲んでい
る缶ジュースのボタンを押す。
「なっ!? 先生…その五百円玉は俺のでは?!」
「んー? 何のことかなぁ? これはボクが拾った五百円だねぇ」
「ひっ…ひどいっす…」
「……嘘だよ、冗談、冗談。君の五百円はこれだよ」
「……これ記念コインじゃないっすか! しかもエリマキトカゲの!」
「喜んでもらえた?」
「喜ぶわけないっすよ! というかやっぱり今使ったの俺のじゃないっすか?!」
「あぁ…もう、普通に五百円玉あげてもつまらないでしょ…」
「いや、どっちにしろつまらないんで普通に五百円玉返してくださいよ」
結局普通に五百円玉を返す。記念コインはどうやら食いつきが悪かった。まぁボクもい
らないから渡してみたけどケン君も要らないらしい。
「さて、ケン君にもやってもらいたいことがあるんだ」
「ん、何をすればいいんすか」
「ちょっと待ってて。いればすぐに見つかると思うんだ」
グラウンドに出て見渡す。昨日見たあれを探すが見つからない。
「何やってんすか?」
ケン君もグランドに出て見渡す。
「……いや、今日はいっか。ケン君、マホちゃんとマナちゃんの様子はどうだった?」
「えっ、うーん。マホが一方的に話しているだけでマナは全く反応しませんでしたよ」
「あれ、なんで反応しないか言ったっけ?」
「確か、みんなのことが怖いんですよね」
「そうだね、だから、学校ではちょっと難しいかもしれないんだよね」
「あぁ、人がたくさんいすぎてビビッて動けないってことっすか」
「そうだね…。最後まで教室に残っているのもみんなが帰ってからじゃないと…」
「帰れないってことっすか…?」
「どう思う?」
「うーん。難儀な性格ですねとしか言えないっすよ…」
「ふふ、価値観なんていくらでも変わるって、変わるんだったら、早い方がいいでしょ?」
「いい方向に行くんでしたらね」
「ケン君はボクがやっていることって良いことだと思う?」
「良いことなんじゃないんでしょうか? だって、マナは人と話すことが出来ない。それ
は大人になった時マナが困る。マナが困らないように先生は立ち回っているじゃないです
か」
「じつはボクは秘密結社の工作員で、この学校の生徒を一つの思想に誘導して優秀な人材
を秘密結社に輩出するよう言われているんだ」
「先生、それは意地悪いっすよ…。その力も頭ん中改造されて手に入れたって言うんです
か?」
「ははは、いいねぇそれ。まぁ秘密結社は嘘だけど。まぁ生徒のためって言うのもあるけ
どそれだけでしている訳でもないんだ」
「あ、そうなんすか。一緒にいると生徒のために頑張る先生にしか見えませんよ?」
「まぁ、周りから見ればそう写るのかなぁ。まぁ、ただボクの中では違うってだけだしね」
「ん…。どういうことですか?」
「意識の問題ってことだよ」
ケン君は曖昧な表情を浮かべる。それでいいと思う。ボクだってよく分からなくなるこ
とはある。
「そろそろ、下校時刻だね。ケン君も今日バイトなんじゃなかったっけ?」
「あっ そうだった…。というかなんで先生が把握してるんすか…」
「まぁ、ケン君は助手だし。いつ使えるか分からないと困るしねぇ」
「あー…そうなんすか…。それじゃ、俺はここで失礼します!」
「はい、気をつけてね」
ケン君は慌てて帰る。後姿を見送ってボクも職員室に戻る。日が沈みかけるグラウンド
には部活に励む生徒の声が響いていた。
「マナにはお兄さんがいるんでしょ?」
「お兄さんってどんな感じなの?」
「あたしは一人っ子だからお兄さんっていうのがどういうのか気になるの」
「兄妹って仲が良いものなのかな?」
「…………はぁ」
ベッドに座るマナ。椅子の背もたれに寄りかかり顔を覗き込むように話しかけるあたしことマホ。
さっきから話してるのは全部あたし。二人いるのに一人プレイ。あぁどうすればマナは
話してくれるのぉーん!
「ふにふにー」
ほっぺを突っついてもちょっとこっちを見るだけですぐに遠くを見てしまう。でも前進
したほうだ。最初は本当に人形に話しかけているのかと思うくらい反応が無かった。つい
ついおっぱいを揉んでしまっても何の反応もなかった時は戦慄したのを今でも覚えている。
あたしは手の平をみながらあの感触を思い出す。どんぐりの背比べだったとしても、あ
たしよりあったかもしれない…。いや、そんなことはどうでもいいの、柔らかかったんだ
から…。いやいや、それもなんか違う。
そう思いつつもほっぺから手が離せない。ついつい突っついてしまう。マナはそれを嫌
がるように九十度回転してあたしに背を向ける。
その動作、ひとつひとつが可愛い。じゃなくて……あぁもう可愛いでいいや。
あたしは椅子に座ったままマナの横に移動してもう一度ほっぺをつつく。
するとまた嫌がってあたしに背を向ける。その小動物のような動きが可愛すぎるッ。
あぁ…抱きつきたくなるわぁ…。でもいきなりそんなことをしたらダメでしょ。道徳的
に考えて。あぁでも、本当ごめんなさい変態で。
マナが横目でこっちを見る。ちょっとは心を開いてくれたのか、それとも、警戒してい
るだけなのか。多分後者だと思う。なぜならあたしははぁはぁ言いながら獲物を狙うよう
にその背中を凝視しているから。まぁ本当に食べちゃうようなことはしないけど。マナの
反応がいちいち可愛い。それが全てであり正義である。
「ねぇ、マナはさ、友達っている? いらない?」
「……」
あたしはベッドに倒れこむようにマナの横に寝転がる。そしてマナの横顔を覗く。俯い
て考えているのだろうか。相変わらず可愛い。
「もしいるならあたしと友達になってよ。もしいらないならあたしを友達にしてみてよ。
お兄さんが知らない色んなことを教えてあげるよ」
「……」
反応がない…のかな? それとも考えてくれてるのかな? 昨日今日とあったばかりだ
から表情から何考えているかは読み取れない。けど、あたしの言葉に反応してくれてるか
どうかはなんとなく分かる…気がする。多分。
あたしは仰向けになってマナを見続ける。リンドウ先生はマナは極端に人見知りで臆病
だって言っていた。あたしとこうやっているだけでも頭の中が真っ白になっているのかも
しれない。なら多少強引にでも、マナを引っ張ってあげた方がいいのかもしれない。
「マナがそうやってずっと黙っているならくすぐっちゃうぞー」
ぺたんこ座りをするマナの膝小僧をくすぐる。突然の刺激にマナは飛び上がるがベッド
の上でバランスを崩し、ベッドから転げ落ちる。
「マナごめん! 大丈夫…?」
足から腰までを覗かしてベッドの下に落ちた。頭から落ちちゃったように見えたんだけ
ど…。というかその体勢からして頭から落ちたよ…。
「いたい…」
ベッドの下からひねり出すようにくぐもった声が聞こえた。
「マナ…大丈夫?」
マナがしゃべった、けど今は大丈夫かどうかを確認しておこう。ベッドからマナが落ち
たところを覗くと、仰向けに落ちて頭を抑えて涙目になっていた。
可愛いッ!! が先に落ちて大丈夫だったかを。スカート捲れてパンツ見えて内股が柔
らかそうだけど、とりあえず、起き上がらせよう。そうしよう。
「頭打ってない?」
後頭部とお尻を持って逆さまのなっているマナを赤ちゃんを抱えるように降ろす。
すると小さく頷く。
大丈夫、ってことなのかな? 言葉を交わしていないけど初めて会話ができた気がした。
マナは立ち上がり時計を見る。そろそろ帰らないといけない時間なのか。そうだ、あた
しもマナも帰ってくる人のための準備をしなくちゃいけない。
「今日はもう帰る?」
マナは小さく頷く。
「うん、また明日」
前のページに戻る/次のページに進む/もくじに戻る/