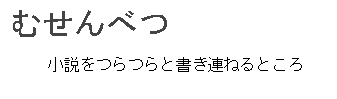4日目1
前のページに戻る/次のページに進む/もくじに戻る/
四日目。チャイムが鳴った。さぁ地獄のホームルームだ。……そう思っただけで別に何
でもないホームルームである。ひとつ違うことはボクが教室から出て行くまで皆じっと椅
子に座っているということだ。
くっ、相変わらず、あの子たちはニヤニヤしながらボクを見る。ボクは逃げるように教
室から出て行く。職員室に戻って、マホちゃんに教室に行っても大丈夫かメールする。
―――大丈夫ですよ!
相変わらず、メールからも元気いっぱいな感じが伝わってくる。ケータイの文面を見な
がら廊下を歩く。
「こらこら、学校にケータイは持ってきちゃいけませんよ」
反射的にケータイをポケットにしまい振り向いてしまった。
「…んっあっははは! 林道先生、今凄く緊張した顔してましたよ。まるで生徒さんみた
いです!」
振り向いた先にはフックンがいた。今のはフックンの悪戯だったのだが、この人はどう
にも子供っぽい…。まぁそこが魅力なんですけどね。
「いやーフックン、何やってるんですか。保険室、空けてていいんですか?」
「今戻るところですよ。リンドウ先生も廊下でケータイなんか見て何やっているんです
か?」
「ボクは今日も生徒の相談に乗るためこれからZ組に行くんですよ。フックンも来ます?」
「何言ってんですか。今保険室空けるなって言ったばかりじゃないですか」
「あぁ、そうでした。それではボクはもう行きますので」
「はいはい、頑張ってくださいね」
フックンはそう言って笑顔を向ける。そんないい笑顔を向けられると自然と笑顔がこぼ
れる。
廊下を歩き一人ニヤニヤする教師。ヤバイ、ヤバイ、ニヤニヤが止まらない。顔の下半
分を左手で隠しながらZ組に向かった。
「先生何ニヤニヤしてるんですか?」
早速マホちゃんに突っ込まれた。
「先生、いいことあったの?」
マナちゃんにも追い撃ちをかけられる。
「いやいや、マナちゃんがマホちゃんと仲良くやっている様子を見て、ボクはうれしいん
だよ」
「何言ってるんですか! あたし達はいつも仲良しよね!」
「ちがうよ」
その時、マホちゃんが一瞬止まったように見えた、がこれは割りといつものことである。
「いつもは仲良くない。だって、マホ、マナのほっぺをつっついてくるんだもん」
頬を膨らましむくれるマナちゃん。しかしそれがマホちゃんにとって逆効果だと知るよ
しもなかった。……ほら、ハァハァ言い出した。が、あえて突っ込みは入れない。
「いいじゃん、いいじゃん。ほらこれはいつものスキンシップだってぇ…」
「いやなの。なんでマホはいつもマナのほっぺをつっつくの? 昨日だって…」
そこで、マナちゃんは止める。マホちゃんはニヤニヤしながらハァハァ言っているが突
っ込まない。
「仲が良いのはいいけどあんまり過激なことはしないようにね…」
「何想像してるんですかー先生。エッチなことはしてませんよー」
「君ならいつかやってしまいそうだから言ったんだよ。ノーマルでいてね」
「先生」
「ん、何? マナちゃん」
「ノーマルって?」
「ん、難しいことを聞くねぇ。口で説明しても伝わらないものだからなぁ。あ、そうだね、
マホちゃんみたいなことをしない人かな」
「わかった…」
「ちょ、ちょっと先生! 変なこと言わないでくださいよ。あ、あたしは変なことなんて
しませんよ!」
「ほら、動揺しているのが見て取れる。ああなっちゃダメだよ」
「うん」
「ひ、ひどい…」
「さて、マホちゃんをからかうのはここまでにして、ケン君はもう帰ったの?」
「あ、はい。えーっとシラボネ君? でしたっけ?」
「うん、鹿羽剛士君。彼が今度の相談者。今回はケン君に頑張ってもらってるけど、どう
んな感じだった?」
マホちゃんとマナちゃんは顔を見合わせる。二人は特に表情を変えず、答える。
「どんな感じっていわれましても…。特に普通に話しかけて普通に会話してましたよ」
「うん」
二人とも特別な印象は無い様子だった。学校では特に何も無かったらしい。まぁケン君
にメールを入れてどんなもんか知ればいいだけだ。「問題」が起きれば、すぐに連絡入れる
ようには言ってある。
今回の生徒は鹿羽剛士。見た目に反して高身長で線の細い男子生徒。のっぽという言葉
が一番似合う生徒だろう。彼ももちろん「問題」を抱えている。マナちゃんが話せるよう
になった日の何日か前に彼をグラウンドで見た。その挙動不審な動き、手にはフィギュア、
私服で暗い夜道を歩いていたら絶対に職務質問を受けているであろう。しかし、職務質問
を受けることは無い。なぜなら彼は夜外に出ないからだ。それだけならなんでもないのだ
が彼は学校以外外に出ないのだ。なんというか極端な生き方をしている。別にしゃべらな
いとかそんなのはない。学校と学校の行事以外ただ一度も外出したことが無いのだ。まぁ
でもこれは大問題とは言わない。マナちゃんと同じで友達がおらず、マナちゃんほどでは
ないが会話が苦手そうな感じだった。というか記憶を覗いて会話しているのが親とだけで
それも一言や二言ぐらいしか話していなかった。
だから、マナちゃんの時のように友達を作れば大丈夫だろう。……多分。
ケータイのディスプレイを眺める。別にケン君から連絡は無い。いつもの壁紙にデジタ
ル時計が時間を刻んでいる。ケン君の連絡が無ければ動けない。後手後手になってしまう
だろうが仕方ない。頭ん中を覗いても見えるのは記憶だけだ。多少、感情も影響して改変
されているがその感情の理由は覗けない。操って答えさせることができるのはイエスかノ
ーの簡単なものだけで、結局のところ本人の口から聞きだすしかないのだ。それにボクの
していることは、防ぐではなく治す。問題が起きないことはいい事だ。そうすればボクは
ただの国語教師だ。こんな「力」を使うことなんてないだろう。人の記憶なんて覗いたと
ころで見なくていいものまで見えてしまうだけだ。操ったところで何の意味もない。あぁ
あと話すことが出来るが、これは使いたくないので省略。
ケータイを閉じポケットにしまう。
「二人とも用がないなら早く帰りなよ」
今日は特に何もなさそうだ。ボクは職員室に戻ろう。
「うお! お前、このゲームやりこみ過ぎだろう…。なんでそんなショートカット知って
るんだよ。というか俺が知っているレースゲームとなんか違うぞ…。なんだよマグロカー
トって…」
「あ…止まると死ぬ…」
「うおおお! おれのマグロがぁ…! 浮いていく…」
「フ…フフフ…」
ゲームのコントローラーを持ったまま画面の中で窒息死した俺のマグロを唖然としなが
ら眺める。横ではシカバネが含み笑いをしている。
「チックショー……ちっとトイレ借りるぞー」
俺は立ち上がり、シカバネの部屋から出て、廊下の突き当たりのトイレで用を足す。ト
イレから出て廊下に出る。シカバネの部屋と廊下では空気が全然違う。部屋の明るさ、広
さ、シカバネの部屋の方が勝っているのになぜかシカバネの部屋はなんか暗くて不気味だ。
なんとなくであるが何か不気味な視線を感じてしまう。暗闇の中で誰かからの視線。そん
な背中や手の先、足の先がぶるっとするものを感じる。ゲームをやっていても何かこう違
和感があってのめり込むことが出来ない。これは決して負けた言い訳じゃない。負けたの
は俺の経験不足…! 俺だって練習すればぁっ…!
リベンジを決意しシカバネの部屋に入る。シカバネはゲームをやめて小さなガラスケー
スを眺めている。中には一番下から歴史の人物のフィギュア、ロボットのプラモデル、ア
ニメキャラのフィギュア、が飾られている。俺の知っているのもあれば全然知らないのも
ある。
「お前、色々集めてんなぁ」
「フ…フフ…フ…」
もしかして、俺が感じていたのってこのフィギュアからだろうか。ちょうどテレビと対
面の位置にあるからこいつらに俺の雑魚っぷりを見られていたわけだ。テレビとガラスケ
ースを交互に見て、ついでに部屋の中を見渡す。当分はこの部屋に来るごとに圧倒される
のだろう。この部屋に飾られているガラスケース。しかし、それ以外にもこの部屋には色々
なものが収集されている。
ミニカーや鉄道模型が手を伸ばせば届く位置に箱から開封されずに飾られている。手を
伸ばせば届く高さにありついつい手を伸ばして触ろうとしたら。
うっ、睨まれた。じっと俺を見ている。そんな見つめないでくれ。やっぱりこういうの
触らないほうが良さそうだな。すんません。
時計が目に入る。もうすぐ七時だ。今日はマホの家で晩飯だったな。マナが来るとか何
とか涎を垂らしながら言っていたな。
「そいじゃ、今日はこれで御暇させていただくぜ」
「あ…あ、じゃあね…」
「あ、そうだ。マグロカート貸してくれないか…? 次遊びに来た時に負けねぇように練
習してぇんだ。ダメかな…?」
「あ…あ、いいよ…それじゃ…はい」
「おう、次はまけねぇぜ。それじゃあな!」
シカバネの家はマンションの三階。とりわけ大きな部屋ってわけじゃないけど小さくは
ない。俺の部屋よりは全然大きいということだけは言える。十二階建てのマンションを背
にしてマホの家に向かう。
「ねぇ、なにこれ…なんで海でマグロやかつおや鮭が泳いでいる中竹の子でスピードアッ
プするのよ」
「ゲームにそういう突っ込みは野暮だぜ? キノコ食べて大きくなるっていうゲームがあ
るんだから。あ、ちなみに竹の子早く使わないと竹に成長して相手にぶつけるためのアイ
テムになっちまうぞ」
「なによそれ…あ、本当だ。竹になってる。なにこれ、これであんたの鮭を刺すことでき
るの?」
「ちょっ待てよ。なんで順位の低い俺を狙うんだよ! 一位のかつお狙えよ!」
「コンピュータ相手にするよりあんた相手にしている方が面白いわよ。ほら死ね!」
「うおおお! おれの鮭がぁ…! 浮いていく…」
「ケン、死んだの?」
「あぁ、死んだ。俺の鮭は短い人生を生き抜いて最後にマグロに竹で刺されて死んだよ…」
「晩御飯の鮭おいしかったね」
「あぁ…きっとこいつもスタッフがおいしく頂いてくれるさ…」
晩飯の焼き鮭を食べた後マホとマナと三人でマグロカートをやったが、なぜか初心者(の
はず)のマホに負かされるという事態だった。俺の鮭は哀愁と血を青い海に漂わせながら水
面に浮いていった。ちなみにマナのカツオは開始早々止まっていたため窒息死した。
「やった! あたしが一位! それじゃあ罰ゲームね! ケンは晩御飯の洗物! マナは
こっちにおいで!」
ちくしょう…焼き魚はコンロ使う。洗うのが面倒臭いからゲームで負かしてマホにやら
そうとしたのに…。
「マホ、きらい…」
そんな声が聞こえた。だが今日のマホは違った。
「マナ、これは罰ゲームなの…」
「罰ゲームってこういうことすることなの?」
「罰ゲームっていうのはね、相手の嫌がることをしなくちゃいけないの。さらにギャラリ
ーが面白がったり喜んだりしてくれないといけないの。だから、これは仕方なくマナにや
っているの。しかも、マナは可愛いからそういう反応がみんなを喜ばすんだよ。ほら、ケ
ンも楽しそうに見てるよ」
キッチンからは見えていない。見えているのはステンレスにこびり付いた焦げ目だけだ。
あぁくせぇくせぇ。
「……」
マナはマホに言いくるめられたのかその後も嫌がる声が聞こえない。俺は焦げ目と戦う
のに専念した。頑張れよマナ。
焦げ目を倒しきり食器を棚に片す。リビングからは二人の声が聞こえる。
「マナ、杜は一位の魚を追いかけて刺してくれるんだって」
「いつ使うのがいい?」
「ケンが一位で調子に乗り出したら使うのがベストよ」
「うん」
「網縄は後ろに設置するタイプのアイテムね」
「これは?」
「ケンが後ろの順位で、もがいている時に止めを刺すのに使うのがいいわね」
「うん」
俺の鮭をどう狩るかをレクチャーしていた。こっちのほうが罰ゲームなきがするんだけ
ど。
その後、俺の鮭は狩られすぎて大海原を赤く染めた。
前のページに戻る/次のページに進む/もくじに戻る/