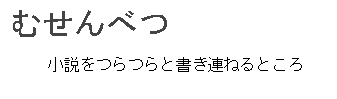しんだあの子2
前のページに戻る/
次のページに進む/
もくじに戻る/
そして授業が終わり僕はレイをみる。レイはひとり黙々と教科書をカバンにしまって
いるだけで、誰にも声をかけられたりはしていなかった。
声をかけるのなら今しかないと思いレイのとなりに行く。
「レイ、アレ返して欲しいんだけど」
そう声を掛けるとクラスがざわついた。
「おいおい、マト君。お前みたいなのがなんで鳳華殿様に声かけているんだい」
クラスの男子生徒の一人がそう声をかけてくる。
「鳳華殿様は忙しいんだ。おまえみたいなのに鳳華殿様の時間を費やしている暇はない
んだよ」
男子生徒は僕の肩を掴みレイに道を作ろうとする。
「いいですわよ、ついてきてくださる?」
レイは目の前で起きている事に気にすることなく、そう言って廊下に出ようとする。
「鳳華殿様! こんな奴に付き合う必要なんて!」
「必要かどうかがどうしてアナタにわかるかしら?」
レイは背を向けたまま淡々と答える。そんなレイに対して男子生徒は表情を慌てさせ
押し黙る。
「それと……わたくしのことは名前で呼んでとおっしゃったはずですわ!」
レイはふんぞり返りながら振り返りそう言い放つ。
しかし、クラスは静まりかえり、誰一人口を開かない。
レイはひとつため息をつく。
「マドカ、行きましょ」
僕は言われるがままに頷きレイについていく。
レイは止まる気配はなくどんどん歩いていく。階段を下りて校舎を出て校門を抜ける。
「レイ、どこまでいくの?」
声をかけるがレイは止まらない。
そんな背中を見て、僕はふと思ってしまった。
レイも逃げているんじゃないか、と。
追われているからじゃない。誰からも追われない、そんな場所にいたくなくて逃げてい
るんじゃないか、と。
「さっきの男子生徒。片淵(かたぶち)と言いますの」
レイは人通りの少ない道で不意に足を止める。
「不思議でなくて? 彼はどうしてわたくしのことを様付けで呼ぶのか」
「それは、まぁ……」
「片淵家の会社は鳳華殿家が出資しているおかげで経営できているんですの。そのせい
で息子である彼は鳳華殿家の娘であるわたくしを畏怖していますの。何か無礼をしてし
まったら自分の家に何かあるんじゃないか、と」
「レイ、ごめん……。話がむずかしくて、よくわからないよ」
レイは振り返り、ため息交じりに笑う。
「つまり、天才であるわたくしの機嫌を損ねると何か怖いことされるんじゃないかと、
びびっているんですわ」
「あーなるほど。だから鳳華殿さまーって言ってるんだ」
「全く、それが機嫌を損ねるって気付かないのかしらね」
もう一度レイはやれやれとため息をつく。
「で、ケータイを返して欲しいのですよね? あなたのケータイはうちの研究所にあり
ますわ」
「えぇ?! どうしてそんなところに?」
「オリトに解析を頼んだとおっしゃったでしょ。うちに行かないければ返せませんわよ」
と言うとレイのケータイが鳴る。「失礼しますわ」
レイはそういって自身のケータイを取り出す。そして返事を二、三回返すと電話を切
り、僕の方を見る。
「どうやら解析は早めに終えたようですわ。オリトがこちらまで持ってきてくださるそ
うよ、よかったですわね」
レイはそういって僕の横を通り過ぎる。
僕はレイがちかづいて来たことにどきっとしてしまった。レイはとてもキレイな顔を
している。どこから見ても絵になるとでも言うのか。他の女子生徒から抜きん出た存在
感だ。その存在感の理由は単にキレイだからじゃないと思う。なんというか立ち回りと
いうか雰囲気がすごいのである。
さっきの片淵君の話もそうだ。きっと僕とは見えているモノが違うんだなと思った。
だからその背中に憧れるのかもしれない。そんな女の子に相手をしてもらっていること
に浮かれている自分がいるんだろう。
「なにボーっとしてらっしゃるの? 戻りますわよ」
「あ、うん、ってどこに?」
「あの女子トイレですわ」
だけどこの異常事態はもうすぐ終わる。ケータイを返してもらえば、いつもどおりの
日常に戻るのだ。
女子トイレの目の前でレイはあしを止める。そして片手を挙げパチッと指を弾くと窓
から先ほどの清掃員、否黒いスーツに身を包んだ老紳士という言葉が似合う男が転がり
込んで、そして何事もなかったようにスッと立ち上がり小さく一礼する。
「お嬢様、先ほどお預かりした携帯電話でございます」
オリトと呼ばれるレイの執事は身を屈めレイに僕のケータイを渡す。
「早かったですわね」
レイはそうオリトさんに言うと。
「少し気になる点がありまして、よろしいでしょうか?」
オリトさんは僕の方を一度見る。レイは「構わないわ、話しなさい」という。
「この携帯電話には電話、メールの機能以外は搭載されておりませんでした」
「子供が携帯するモノとしては十分ですわね」
「そうですね、しかしこれにはもうひとつ――恐らくですが、開発者によって搭載され
た機能があります」
「オーバーライセンス持ちってことですわね」
「さすがですお嬢様。申し訳ございませんが、そのためこの携帯電話は解析という解析
をいたしておりません」
「オーバーライセンス持ちのブラックボックス。開発者だけの理(ことわり)ゆえに既
存の公式はあてはまらない……」
レイはオリトさんからケータイを受け取る。
「オリト、ご苦労様でした。下がってよいですわ」
レイがそう言うとオリトさんは一礼し廊下の角を曲がり見えなくなる。するとレイは
僕の方に振り返り僕の手を取りケータイを握らせる。
が、僕の手を握ったまま離さない。
「マドカ、これをお返ししますわ。でー……そのぉ、お願いがあるんですが……」
レイは今までとは一変して歯切れの悪い様子で僕を見る、というよりケータイを見て
いる。ケータイをみる目は獲物を逃がすまいとぎらつく獣みたいだ。
「このケータイの何がオーバーライセンスに引っかかっているのかを教えて欲しいので
すが」
「そ、そんなこといわれても……。ぼくはこれをもらっただけでなんのことかわからな
いよ」
「なら、このケータイを貸して欲しいのですがっ」
レイは僕とケータイを握る手を祈るように目の前に持ってくる。
「いや、ダメだって。僕に電話をかけたのにレイが出たら相手は困るし。それに何より
僕が困るよ」
「なら、いまだけでいいですわっ。お願い致します! このとーり!」
レイはぐいぐい顔を近づけ、鬼気迫る表情で懇願とも脅迫ともいえるような攻めを見
せる。僕は廊下の端まで追い詰められる。
「わ、わかった。じゃあいまだけ! いまだけは貸すから!」
そういうとレイの顔は満面の笑みになる。
「それじゃあさっそくお借りしますわ」
レイは僕の手から滑らすようにするりと抜き取る。もし僕が拒否していても抜き取る
ことが出来たんじゃないかといえる手つきであった。
レイは窓辺に腰掛けてケータイをいじりだす。僕は少し離れた位置でケータイをいじ
る手を眺める。白くて細く、それでいて小さな手。身長はそんなに変わらないというの
に所々に女の子らしさというものが見え隠れしている。
「さっきからこちらを窺っているようですか? 別に壊したりなんかしませんわよ」
「いや、なんだかその手つきをみていると扱いに慣れてそうだから、心配はしてないよ」
「なら、わたくしを見ていたのですね。たしかにわたくしは客観的に見てキレイ、うつ
くしい、かわいいなど表現されますわ」
「い、いやべつにそういう目でみていたんじゃ……」
「あら、そうなのですか? でもそういう目ではみない方がいいですわよ。見た目は良
くても中身が変ですからね。たいていの方はわたくしと話したあとはいなくなってしま
いますわ」
「まぁたしかにその性格は変だと思うけどべつにいいと思うよ」
「あら、貴重な少数意見ですわね。それはなぜかしら?」
「だって、もしレイが普通の女子生徒だったら、僕は女子トイレに潜む変態として先生
に言われてたと思うし」
「おかしくはなくて? あなたがトイレにいたのはいじめを回避するための手段として
であったのでしょう? ……まぁあなたにそのような趣向があるのかどうかは図れませ
んが」
「君はそういう風に分析してくれるけど、他はそうもいかないよ。他人事になるとおも
しろおかしくするために平気で歪んだ噂をするし。その噂が大多数の認識になれば、そ
れがほんとうの評価になっちゃうしね」
「小学生のいうことではありませんわね。そんなことを他人に話せば確実に相手は引き
ますわよ?」
「うん、だからこんなことを話したのもレイが初めてだよ。レイはどういう風に反応す
るのかなって」
「天才であるこのわたくしを試したというの?」
「そういうわけじゃないよ。単にレイみたいに変な人なら、そういう文句をいっても、
ちゃんと聞いてくれるかな、って思った」
「こんなほとんど赤の他人のわたくしに話さなくても家族にいえばよいのではなく
て?」
「母親はあまり僕のことが好きじゃないんだ。それに父親は仕事であまり家にいないし」
「そういうことですのね。あなた居場所がないのですね。それであなたの知り合いの方
はこのケータイを渡したのかもしれないですわね」
「どういうこと?」
「お昼休みの時、あなたにいくつか質問しましたの、覚えていらっしゃる?」
「……質問されたのは覚えているけど内容は忘れたかも」
「わたくしは、このケータイを誰から貰ったか、電話の相手は誰か。この二つを聞きま
した。天才であるこのわたくしによる憶測ですがケータイを下さる方なんてそうおりま
せんわ。知り合いのおばさまはきっとあなたを気にかけてくださったのではなくて?」
「心配してくれてるってことか……。なら、僕に友達がいないのも知っているのかも」
「だから相談相手なんてものを用意したんですわね。――けど問題は、その相談相手で
すわ。そんな簡単に人一人、ましてや子供一人の相手をするために用意することなんて
困難ですわ」
レイはケータイを再び操作して僕に画面を見せてくる。アドレス帳の『ミミ』が選択
されている。
「このケータイには今日まで用意されている基本的な機能が全く搭載されていませんわ。
そしてこのアドレス帳もおかしな点はありません。ただこの『ミミ』という方には違和
感を覚えますわ」
「そんなにきになるならかけてみる?」
「いいのですか? あなた以外の人が電話をかけても」
「なんで? べつに電話をかけるくらいで問題があるの?」
「えぇ、オーバーライセンスの技術が使われている可能性のあるケータイですからね」
「オーバーライセンス……ってなんなの?」
「オーバーライセンスというのはまだ世間に公表されてない技術。それらを総じて超過
学といったりしますわ。そんな超過学をもつ証ですわ」
「それってすごいものなの?」
「えぇ、多分マドカが想像しているものより遥かにすごい技術ですわ。もう科学とはい
えない魔法のように見えてしまうような、そんな技術ですわ。残念ながらその内容は他
言していいものではないので説明できないですけど……そうですわね。例えるなら空飛
ぶ自動車が実はもう開発されている、とかですかね。反重力場に特殊合金のボディ、光
学迷彩、あ、でもうちの施設では気圧変化に対応できませんわね、それに自動車という
フォルムじゃあ空は飛べませんわね……」
「あのー……」
「……! 失礼しましたわ。つまり! とんでもない技術をもっている者に与えられる
証ですの! 説明になってはいませんけどこれで納得してください」
「ま、まぁとりあえず納得しとくよ」
「本来は知らない者には説明をしてはいけないのですけども、あなたはオーバーライセ
ンスのケータイをもっている以上関わっているということですわ。それにしてもその知
り合いの方もずいぶん思い切ったことをしますわね。あなたみたいなド素人を関わらせ
るなんて」
レイは冷ややかとも、哀れむような目を僕に向ける。だが、こっちとしてはなんの実
感もないことなので、そんな目を向けられてもどういう顔をすればいいのか困る。
「とりあえず、そのケータイにすごい秘密があるんでしょ? で、レイは『ミミ』があ
やしいというわけで」
レイは「そうですわ」とケータイとにらめっこしている。
「さっきも言ったけど、かけてみようよ。僕だって興味あるし」
「なら、まずあなたが電話をかけてみるのはどうかしら。というか、普通に正体を聞い
たことはありますの?」
「いや、ないよ」
「決まりですわね」そういってケータイの発信ボタンを押してレイは僕にケータイを差
し出す。
僕はケータイを耳にあてる。二度目のコール音がなった時
「もしもーし、ミミです。なんか反応なかったですけど、大丈夫でしたか?」
「大丈夫だよ。色々あったけど特に何もなかった」
「何もなかったんですか? こっちはもう色々ありましたネ。もうすごいいじられちゃ
って大変だったんですからネー。聞いてくださいよ。もう、なんか中のデータ覗かれそ
うになって、なんていうんでしたっけ? デリカシーのない人でしたネ。でもあたしを
みたら、いじるのやめてかえってっちゃったんですけどネ」
僕はミミの話に相槌を打つ。なんの話しをしているのかはわからない。横からレイが
僕を見て早く聞きなさいとにらみをきかせてくる。
「あぁちょっといい? 聞きたいことがあって電話したんだけどさ」
「んーなになになんでも聞いてくださいネ」
「ミミって、そのー……どこにいるの?」
「ミミ? ミミはネー。んー『ここ』にいますネ」
「『ここ』って……どこ?」
「この『ケータイ』の『ナカ』ですネ」
……いまミミはなんていった? ケータイのナカ、なか、中。
「ケータイの中と言っているんだけど」僕の頭ではわからないのでレイにきく。
「なにがですの?」眉をひそめ聞き返すレイ。
「どこに住んでいるかを聞いたら『ケータイの中』だそうです」
「わかりましたわ! その子自体がオーバーライセンスですわね。『どういうこと?』っ
て聞かれる前に説明しますけど『ミミ』は電話の向こうから話しているのではないので
すわ。電話、ケータイの中にデータとして存在しているんですわ」
「え……っと、つまり……どういうこと?」
「……ヒトと会話できる頭脳と口と耳がこのケータイに備わっているということですわ
っ。これでよろしくて?」
「はい……」
「で、その頭脳と会話するにはアドレス帳から『ミミ』を選べばいいということですわ
っ」
「はい……よくわかりました」
「ふぅ……。天才であるこのわたくしをここまで苦戦させるとは……やりますわね」
「なんか、すみません……」
「まぁ、わたくしのいったことは何の検証もしていない仮説にすぎませんわ。一応ミミ
に聞いておいた方がいいですわね」
レイは優雅に手の平を差し出し、聞いてごらんなさいと示す。僕はレイの先ほどのヒ
ートアップしていた様子とのギャップに複雑な表情でケータイを耳を当てる。
「ミミ今の話聞こえてた?」
「聞こえてましたネ。そうですネ。その通りです。……そういえばそこにもう一人いる
んですよネ…………アー、アー聞こえますか?」ミミはケータイの中から自らスピーカ
ーモードにし僕以外にも声を届くようにする。
僕はここで初めて本当にケータイの中にいるということを実感し少しのけぞってしま
う。
「えぇ、聞こえていますわ。そちらにはわたくしの声は届いていらっしゃるのかしら?」
「届いてますネ。ミミの名前はミミっていいますネ、よろしくですネ」
「わたくしは鳳華殿 怜と申します。以後お見知りおきください」
レイは胸に手を当てちいさく一礼する。
「こちらもよろしくおねがいしますネ」
「いきなりで申し訳ないのですが、ミミはどういう目的で作られたかをご存知ですか?」
「ミミですか? ミミはマドカの話相手をするようにと所長にいわれていますネ」
「所長? 所長というのはアドレス帳に入っていた『開堂 則子』のこと?」
そうですネ。スピーカー越しから肯定するミミ。
「開堂則子……サイバーテクノロジー関連で聞いたことある名前、ですわね。あとで確
認しておかないといけませんね。……他に何か指示をされていたことはあります?」
「んーないですネ」
「話すこと自体が研究材料なの……? だったらこんな子供にケータイを丸ごと渡しっ
ぱなしにしないはず……。それとも日常会話をさせてそれでそのデータを取ろうとして
いる? だったら研究はほとんど最終段階……。けど何のための……人型ロボットなど
に搭載させる機能……。いや、でも、まだ、この技術は現代社会にはでないはず……。
世に出るならもっと情報が出回る……」
レイはうつむき口元に手を当てぶつぶつと何かいっている。
レイに声をかけても返事はなくひたすら何か呟いている。と思ったら
「マドカッ」レイは声を張り上げこちらにふんぞり返るように振り返る。
「ちょっといいかしら?」
「はいなんでしょうか」その威風堂々とも唯我独尊ともいえる姿に思わず敬語が飛び出
す。
「わたくし、ミミが何の目的で作られたか、気になってしまいましたわ」
「そうですか」
「いいたいことがわかりますわよね?」
「まさか! ケータイをよこせと……?」
「ちがいますわッ。わたくしがそんな粗暴に見えまして?」
「はい……」
「ふぅ……どうやら、あなたには認識を改めてもらう必要がありますわね。それも兼ね
て、わたくしも極力あなたたちと共に行動しますわ」
「え、どういうこと? なにをするの?」
「恥ずかしいですが、あなたにはちゃんと言わなきゃ伝わらなさそうですわね……」
レイは一つため息をついてやれやれといった仕草をする。そして一つ咳払いをして
「わかりやすく言えば、友達になりましょう、ということですわ。あなたそういうのい
ないでしょうしね」
僕の初めての友達だった。同年代の気の許せる相手。それはかけがいのないもので。
特別で。笑って優雅に手を差し出すレイ。その手は、触れていいものか、わからず
「あ、ありがとう」
僕はそう口にしていた。
前のページに戻る/
次のページに進む/
もくじに戻る/